概要
始めに
新井潤美『不機嫌なメリー=ポピンズ』についてレビューを書いていきます。
リンク
階級社会英国の言語、家事使用人、男性、ファンタジー、マイノリティ
階級社会英国を舞台とする作品について、社会史的な部分も踏まえた解説集です。もっぱら、言語、家事使用人のバリエーション、男性の立身出世、ファンタジー・SFジャンルにおける英国社会の再現、マイノリティ英国人の文学というテーマについて解説しています。体系的に英国社会について学べる訳ではないですが、取り上げられている作品も豊富で楽しいエッセイです。
広く浅く。体系性には乏しい
広く浅くな作品論、作家論です。もう少し詳細な読解のためには別の文献が必要になりそうです。また、英国社会、文化について体系的に学べるものではなく、階級制度やその中での実践、慣習にテーマを絞っています。





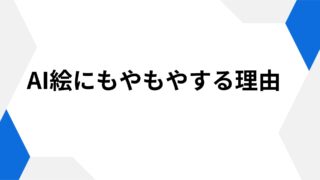
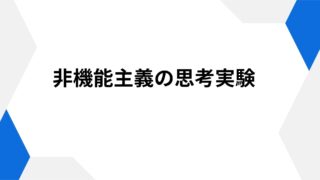






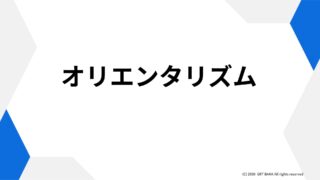

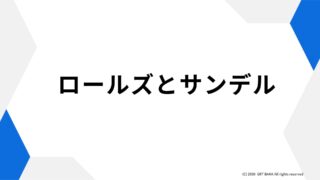
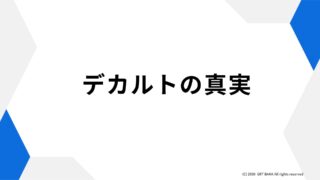





コメント