はじめに
バルト「作者の死」とは何か。テクスト論との関係やその可能性を解説していきます。
- バルト「作者の死」とは、作者ではなく、読者に着目しようとする発想。
- その後デリダの脱構築批評やニュークリティシズムが相まって、テクストそれ自体に着目し、作者をテクストから切り離すテクスト論が発生
- バルト的読みやテクスト論は、アカデミズム的な解釈としては不適合
- それでもバルト的問題意識は、イデオロギー批評、創作、教育の分野で意味を持ちうる
コンテンツ
バルト「作者の死」とバルトの挑戦
ロラン=バルトは、「作者の死」で知られるものの、『サド、フーリエ、ロヨラ』の序文にて作者の回帰について語っており、バルトの批評意識は、もっぱら1.読書の快楽とそれによる自己実現、創造性に着目する読書の倫理学/哲学的側面2.伝統的な実証主義的作家論、作品論への申しだてにあります。
バルトはテクスト論的なラディカルな反意図主義的批評のルーツのように評価されがちなものの、テクスト論はむしろデリダの脱構築批評に依るところが大きいです。バルトは多くの作家論を手掛けていて、ジュディス=バトラーのように薄い内容を極限までレトリックで水増しするスタイルによって主張をくみ取りにくくもあるけれど、キャリアの中での主張をみていくと、およそ制限的意図主義(作者の意図は作品の本質になんらかのレベルに影響するものの、それに還元されるべきものではない)の立場と評価できます。
「バルトは作者の死によって、作者ではなくテクストそれ自体と向き合うことを企図した」という主張をみたことがあるけれど、バルトが目指したのは読解における読者の主体性、創造性の積極的評価と、実証主義的伝記研究による作品論への批判だから、そういう意図でもない感じ。
デリダの脱構築批評とテクスト論
バルトと並んで、テクスト論に寄与したデリダに関して補足すると、しばしば「テクストの外部はない」というフレーズがテクスト論の起源のように語られるものの、これはテクストの外部に作者は居ないとかそういう意味ではなく、あらゆるものはテクストであり、テクストの他はないという汎テクスト論的言明です。
それではなく既存の枠組みの硬直化を批判的に乗り越えようとするイズムを妊む脱構築の発想がテクスト論の反意図主義を形成しています。
デリダの脱構築批評もバルトの問題意識と重なる部分は多いですが、デリダはバルトほど読者の主体性や創造性の評価を重視しているわけではなく、むしろ伝統的な実証主義的伝記研究の硬直化の招く弊害を共有しています。
テクスト論の起源
テクスト論においてしばしば言及される「テクストそれ自体と向き合う」という態度は、表面的にはポスト構造主義の成果のように見えるものの、実際にはデリダやバルト自身の思想に由来するものではありません。
この発想はむしろ、20世紀半ばのアメリカにおける新批評(New Criticism)が、構造主義や脱構築を経由して再輸入された結果です。新批評の理論家たちは作品の意味を外的要因ではなく「作品それ自体」に見いだすべきだと主張しました。彼らにとって作品は、外部から独立した構造的有機体であり、その統一や緊張、アイロニーといった内部構成を分析することが批評の任務でした。ここでいう「作品それ自体」こそ、後に「テクストそれ自体」と呼ばれる発想の原型です。
この内在主義的読解態度は、1960年代のフランス構造主義や記号論の一部によって理論的に精緻化されます。ソシュール言語学に依拠した構造主義は、言語的構造の差異体系を重視し、テクストを社会的・言語的コードの結節点として把握しました。バルトもまたこの流れのなかで、初期には「作品」を「テクスト」と区別し、前者が物質的完成物であるのに対し、後者は言語的エネルギーの運動そのものであるとしました。
バルトの「作者の死」は構造主義的記号論を背景に、作者の意図や心理を解釈の基盤とする伝統的読解に対して反意図主義を明確に打ち出した。しかし、バルトが強調したのはテクストの多義性と遊戯性であり、「テクストそれ自体」への没入ではなく、むしろテクストが生み出す無限の意味生成、読者の生成的行為でした。
これに対し、デリダにとってテクストとは、言語的なものに限定されず、あらゆる存在・経験・意味が差延のネットワークのなかで構成される場です。したがって、テクストは決して「それ自体」で存在することはなく、常に他のテクスト、他の痕跡、他者への関係の中でしか現れないのです。ゆえに、デリダの思想において「テクストそれ自体と向き合う」という態度は論理的に不可能であり、そのような発想は彼の哲学の中核である差延と痕跡の運動に反します。
ところが、1970年代後半から80年代にかけて、英米圏でデリダが受容される過程において、「すべてはテクスト内部で完結する」という観念へと変質していきます。いわゆる「イェール学派」(ポール=ド=マン、J.ヒリス=ミラー、ジェフリー=ハートマンら)は、デリダの思想を文学批評の実践へと応用し、作者・読者・現実世界を排除した「テクストの自己運動」として読解を展開しました。この英米的脱構築批評こそ、今日「テクスト論」と呼ばれる潮流の原型であり、「テクストそれ自体に向き合う」というスローガンが定着します。
しかしこの態度はデリダの思想的文脈から見れば奇妙でもあり、デリダが問題化したのは意味の閉鎖性ではなく、むしろ「開かれた差延の網目」であり、「テクストそれ自体」などという概念はロゴス中心主義の再演です。
「テクスト論の反意図主義」や「テクストそれ自体と向き合う」という理念は、デリダの脱構築やバルトの記号論から直接生まれたものではなく、アメリカ新批評の内在主義的伝統とポスト構造主義的語彙が混淆した、受容史的二次生成物といえます。新批評的な「意図の誤謬」論と、デリダ的な「外部の不在」概念が表層的に結びつくことで、「意味はテクスト内部にのみ存在し、作者も読者も介在できない」という極端な反意図主義が形成されました。
バルトとフーコーにおける「作者」
バルトは構造主義に影響されています。ポスト構造主義のフーコーも「作者とは何か」(講演)で「作者の消滅」を語っているものの、フーコーは構造主義を踏まえて、主体が位置する共同体の背景にある原理や体系(言語やその他規範、システム、秩序)によってその行動(発話、信念)が決定づけらる旨に言及する向きが強い一方、バルト「作者の死」は、伝統的な実証主義的伝記研究と作品論、作家論への牽制の意味合いが顕著です。
バルトが実証主義的伝記研究に抱いていた懸念は、バルトも好んだプルースト(『失われた時を求めて』)とサントブーヴの間に交わされた論争と重なる部分が大きく、プルーストは、件の論争において、サントブーヴが肯定する実証主義的伝記研究、作家論の限界を主張し、経験的に示せる資料から解釈されうる作者のパーソナリティや信念には還元できないテクストのニュアンスがあるとみて、そこには作者自身の深層心理が何らかの形で現れているとみて、そのようなテクストとしてバルザックなどの作品を擁護しました。
バルトに対する個人的批判と評価
しかしここで私から批判的に言及すると、プルーストやバルトの懸念を深刻に受け止めて、偏に作者の伝記的書誌的資料の収集と解釈によっては到達できない作者の深層心理やテクストにおけるその現れがあるとしても、それは決して書誌学的伝記的な実証研究による作者の意図や信念の整理、解釈のプロセスであったり、それとの作家のテクストとの関連性を評価/解釈することの価値をそう下げるものではなく、確かに作家論における作家の信念や意図の解釈の硬直化がもたらす弊害はありうるとしても、その程度の批判的視座は書誌学的伝記的な実証研究による作者の意図や信念の整理、解釈のプロセスであったり、それとの作家のテクストとの関連性を評価/解釈することの価値をそう下げるものではなく、確かに作家論における作家の信念や意図の解釈の硬直化がもたらす弊害はありうるとしても、その程度の批判的視座は今日分析美学の方面でも主流な制限的意図主義の立場は前提とするところでしょう。
正直、バルトの発想からアカデミズムにおける真理探究のための分析枠組みやプロセスを構築するのはなかなか難しいと思うし、バルトが図ろうとした読書における読者の主体性と創造性の評価は、むしろアカデミズムを離れた、倫理的側面、創作的営為におけるその効用として積極的に捉えられます。
バルト的読書の可能性
例えば、ゲーテ『ヴィルヘルム=マイスターの修行時代』は、シェイクスピア『ハムレット』への批評性が伺え、ここには作者としての(既存のアートワールドにおける)テクストの読者の主体性、創造性の発露が垣間見え、同様のコンセプトはジョイス、フォークナー大江健三郎、ナボコフ、村上春樹など、枚挙にいとまがないものの、多くのモダニズム作家に通底します。
また、教育の現場おいても、テクストの読解を通じた生徒の主体性や創造性の発揮は、アートワールドのなかでの公共性の涵養として教育的効用を評価できます。
他方で、アカデミズム的批評、読解においてバルト的なアプローチを役立てようとするなら、フェミニズム批評、ポスコロ批評など、イデオロギー批評の分野に限定されると感じます。
フェミニストやマイノリティが既存のテクストに触れ、そこからの違和感をもとに主体的なテクスチャー解釈を試みるとき、テクストの潜在的な加害性、倫理的瑕疵が浮き彫りになることはありうると思います。
参考文献
・石川美子『ロラン・バルト 言語を愛し恐れつづけた批評家』


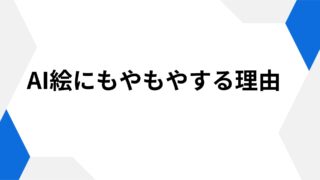



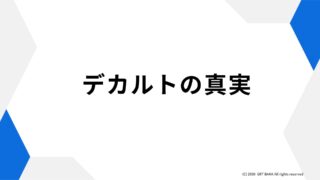



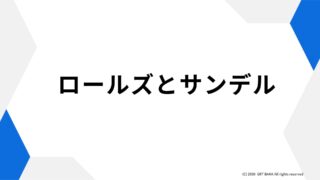



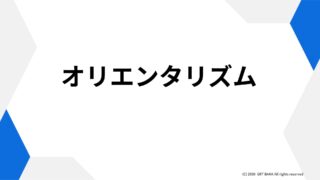



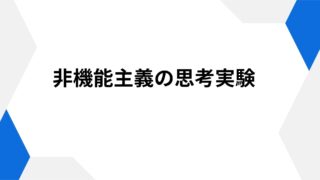



コメント