コンテンツ
コギト
コギト(我思う、故に我あり)は、『方法序説』や『省察』で展開された有名なテーゼです。
デカルトはまず、あらゆる信念を疑う「方法的懐疑」によって出発します。感覚は誤るかもしれないし、数学的真理ですら「悪しき霊」にだまされている可能性がある、と考えます。しかし「疑っている自分」「思っている自分」そのものは疑えません。そこから「我思う、故に我あり(Cogito, ergo sum)」が導かれます。これは自己存在の確実性を示す「第一原理」です。
コギトによって「自分の存在」は確実になったものの、それだけでは外界の存在や科学的認識の確実性を保証できません。そこでデカルトは「完全で無限の存在(神)」を前提にして、認識を保証しようとします。
神の存在証明
デカルトの神の存在証明はいくつかあります。観念論的証明(第3省察)では、私は有限で不完全な存在であるが、「無限・完全な存在」の観念を持っているが、不完全な存在が自力で「完全の観念」を生み出すことはできないため、その原因として、実在の「完全な存在(神)」がなければならないとします。
本質からの証明(第5省察)では、三角形の本質に「三つの角の和が二直角である」が含まれるように、神の本質には「完全性」が含まれ、完全全性には「存在」も含まれる(存在しない神は完全ではない)、よって神は存在するとします。
神は「完全で善なる存在」なので、人間を欺くことはありません。したがって、明証的に把握される観念(「明晰判明な観念」)は真である、と保証されます。この保証によって、数学的真理や外界の存在が信頼できるものとなり、科学的認識の基盤が成立します。
既存の要素とデカルトに固有の要素
アウグスティヌスは『神の国』や『三位一体論』で「自分が疑っていることは疑えない」という議論を展開していました。つまり「懐疑しても消せない主体の確実性」という発想自体は既に存在しています。
アリストテレス以来の「不動の動者」、アクィナスの「五つの道」(存在論的ではなく因果論的証明)、アンセルムスの「オントロジー的証明」(神は「それ以上大なるものが思考できない存在」であるから存在しなければならない)など、神の存在証明も既存のものです。
デカルトに固有の要素は、方法的懐疑を徹底し、「疑いに耐える確実性」を出発点としたこと、神の存在証明を「存在論の一部」ではなく「認識論の保証装置」として使ったことです。
神学的伝統を受け継ぎながら、神を啓示や信仰の対象よりも「科学的認識を保証する存在」として設定したのでした。
科学的実在論とデカルト
デカルトもコギトと神の存在証明が誇張されるけど、凄く極端なことは言ってなくて科学的実在論的なことです。
“私は思う”から、そのレベルで存在は正当化される。それだけでは認識論も科学も無限の懐疑の対象になるから、神学で伝統的な超越論的な存在の前提で、神によって真理を担保するという感じです。
コギトの論理は、アクィナスやスコラ哲学で既に用いられていたものであり、カトリック信徒であったデカルトは、コギトや神の存在を新たに証明しようとしたのではなく、既存の理屈を追認する形で、認識論上の超越論的な真理の調停的システムとしてそれを位置づけたのです。
古典的な科学的実在論は、”対応説的な真理の存在を前提とすれば科学的実践が「うまくいっていること」が真理相対主義に陥らず説明できる。だから、超越論的な経験不可能の真理を前提する”みたいな発想だけど、それと近いです。
心の哲学
しかし実際のデカルトは、心を実体としての心というよりも、働きや機能のまとまりとしての心として捉えていました。想像・注意・判断・意志といった区別は、別の魂の機関が分かれているというより、むしろ心がいくつかの処理方式をもった統合システムであることを示しています。
この意味で、デカルトは素朴な実在論的二元論よりも、かなり機能主義的な二元論に近いです。身体は物理的に働くシステム、心は情報処理のシステムであり、両者が相互作用するという構造を想定していたといえます。デカルトが松果腺を重視した理由も、生理学的にそこが統合の中心のように見えたからで、あれは精神の座を神秘的に決めつけたのではなく、当時の科学知識で考えうる推測でした。
デネットは物理レベル(脳の物質的構造)と意図的レベル(信念・欲望といった抽象的記述)をはっきり分け、それぞれ異なる枠組みで説明しようとしました。デカルトも、身体の仕組みは延長実体として物理法則で捉え、心の働きは別の原理で説明しようとしたのです。違いはデネットが”物理的一元論+複数の記述レベル”という自然化ルートを取ったのに対し、デカルトは二つの実体という形而上学的枠組みを残したということです。階層を分けて説明するという発想自体は、むしろよく似ています。
またデカルトの心の描き方は、現代心理学でいう 二重過程理論に近いです。デカルトは、感覚や想像は誤謬が入りやすく、判断や理性的認識はゆっくり慎重に働くといった区別をしており、これは今日の直感的・自動的な”システム1″と熟慮的・統御的な”システム2″という分け方に驚くほど重なります。デカルトが誤謬は意志が知性の限界を越えて拡張することで起こると考えた点も、反射的反応と制御的判断のねじれという現代的モデルと相性がよいものです。
これに対してカントは、心のはたらきを”感性(空間・時間という形式に従う受容)””悟性(カテゴリーによる統合)”といった先験的な枠組みとして固定してします。つまり、人間の心がどのように情報処理をするか、という可変的な層をほとんど持たない仕組みです。そのため、カントのモデルは認知科学のようなプロセスの追加や階層の拡張を受け入れにくいです。感性と悟性は、あらかじめ決められた条件として働くのであり、そこにシステム1的な自動処理層や、深層の分散表象などを割り込ませる余地がありません。
デカルトはしばしば思われているよりもずっと現代的で、心を複数の処理系の統合として捉える方向性に開かれていたと言えます。
参考文献
・ドュニ・カンブシュネル (著), 津崎良典 (翻訳)『デカルトはそんなこと言ってない』










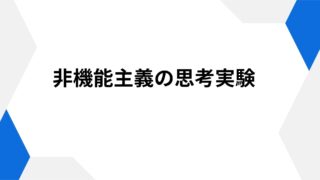








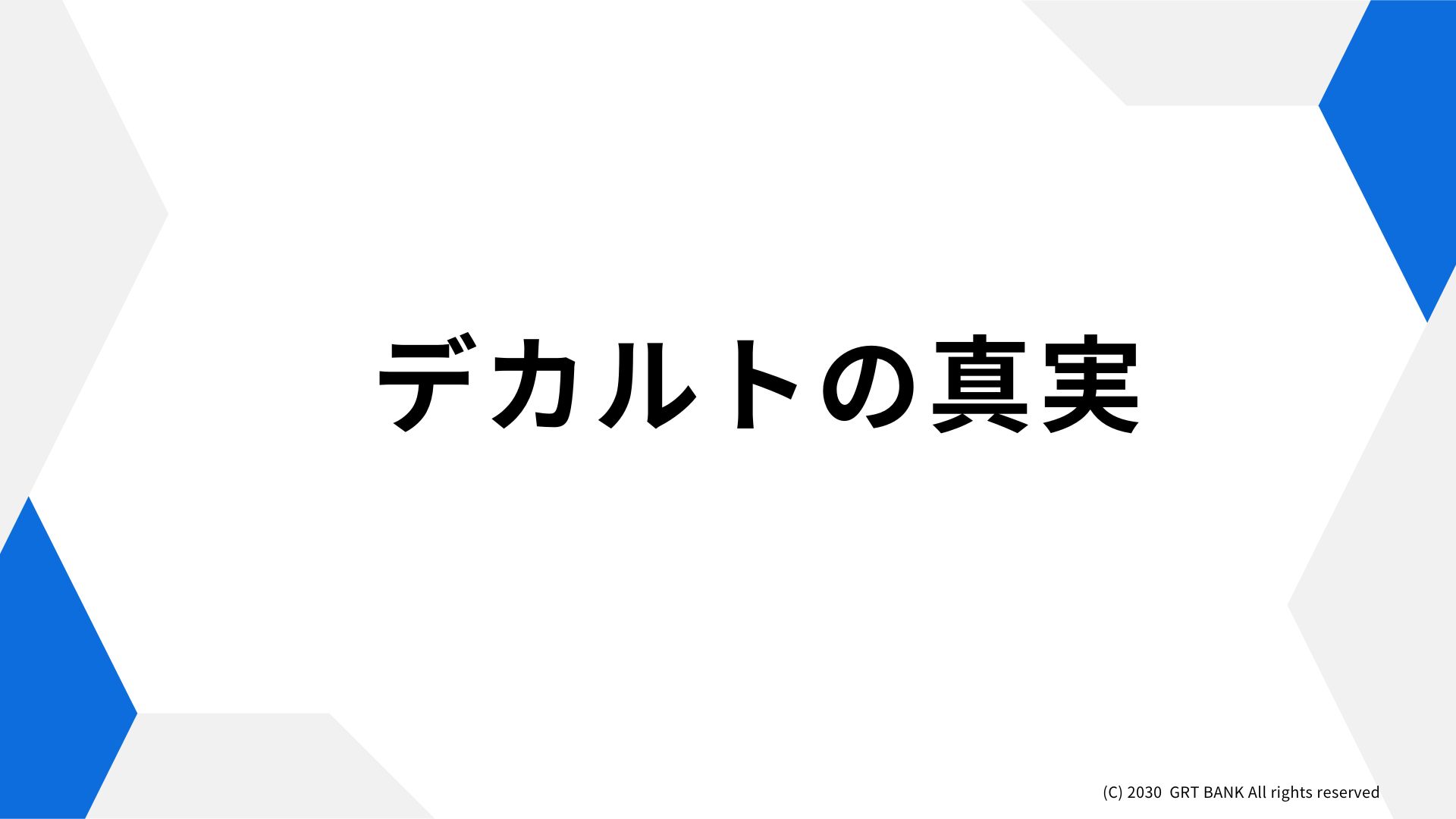


コメント