始めに
サルトルとレヴィ=ストロースの論争と相違点を解説していきます。
- サルトルもレヴィ=ストロースも、エージェントが共同体のなかでその歴史、文脈、制度、秩序にあるレベルで行動を決定づけられるという抽象化の方向性は両者に共通する。
- サルトルはマルクス主義の唯物史観を踏まえ、エージェントが置かれる歴史性について、およそ単線的な見通しを考えていたもののレヴィ=ストロースはそうではなく、また倫理学としての性質からサルトルは自由意志の効用や力を過大に見積もったが、レヴィ=ストロースは、サルトルよりも強く、それは共同体のなかの制度、歴史性、秩序などに決定づけられるとみた
- また認識論的基盤の設定が異なる
コンテンツ
サルトルとレヴィ=ストロースの対立
サルトルとレヴィ=ストロースは両者の間で交わされた論争で知られるものの、この2人の抽象化のベクトルはそんなに方向性を異にするものでもありません。
レヴィ=ストロースが主に批判したのは、1.サルトルのマルクス主義哲学の踏まえる実証主義的歴史モデルとしての唯物史観の西洋中心主義批判、2.自由意志のレベルに関する見通し、が中心です。サルトル『弁証法的理性批判』が踏まえるマルクス、マルクス主義における唯物史観はオンタイムの実証的モデルで、それに対する批判がまずあります。
レヴィ=ストロースの構造主義は、人間が普遍的に持つ原理をもとにして、「未開民族」の共同体にも高度なアルゴリズムを背景に持つ制度、規範といった文化的体系が発展されていることを発見し、唯物史観の西洋偏重の実証モデルに異を唱えました。
レヴィ=ストロースの批判からサルトルを擁護してみる
次に2の自由意志をめぐる論争ですが、留意しておくべきことはサルトルの場合、そもそもその実存主義はハイデガーから継承する倫理学的特徴を備えるものであるから、自由意志の効用や力が強調されやすく、倫理的理想の前提となる自由意志概念がインフレしやすいのはやややむを得ない文脈があります。
またサルトルの実存主義も、世界の中でエージェントが相互的役割期待の中におかれていて、それによる秩序、システム、規範のなかで自由が制約を受けうることを言っているほか、唯物史観を前提とするなど、世界のなかのエージェントの行動をなんらかのレベルで決定づける歴史的文脈を想定していて、こうした抽象化の方向性自体はレヴィ=ストロースとそう違えるものでもありません。
レヴィ=ストロースの固有性
サルトルもレヴィ=ストロースも、カント、ヘーゲル、マルクスを継承し、主体と環境の相互作用の中で社会を構造化する発想は共通します。
ヘーゲルの本質論は、分析哲学のそれとは異なる直感に根ざすものだけど、まずカントの認識論の物自体/現象の二元論を批判し、両者の弁証法的な統合的ダイナミズムのなかで、本質/実存を定義していて、本質は分析哲学における固定的な核ではなくて、存在の反照的運動として本質を捉える感じで、その後のマルクス、実存主義への影響は大きいけど、影響を受けたアリストテレスの形相論とかスピノザの自然主義もそれと近い直感に根ざす感じといえます。
ヘーゲルにおいては、歴史は「本質や概念が歴史を通じて自己展開する運動」として存在論的、歴史的に基礎づけられるのに対し、レヴィ=ストロースにおいては、体系は「人間精神の普遍的構造が文化に投影された関係のネットワーク」として認識論的に強固に基礎づけられ、歴史はその変換の連続にすぎません。
ヘーゲルと比べるとこのように、モデルとしての連続性は大きいものの、認識論的な基盤(構造)を強固に設定し、体系を強固に固定的な基盤に根ざすものとして捉える点でヘーゲルと相違します。
他方で、サルトルはヘーゲルを踏まえ、実存を本質より優位に置いたものの、認識論的な、強固な固定的な基盤を設定しない点ではヘーゲルとむしろ重なります。

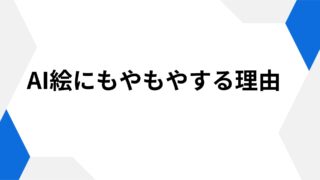

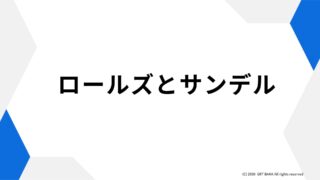



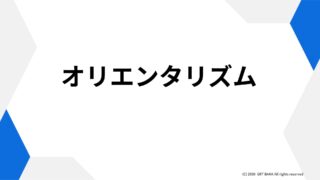








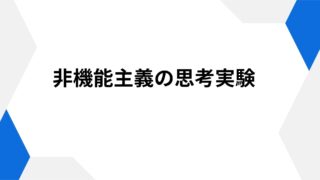

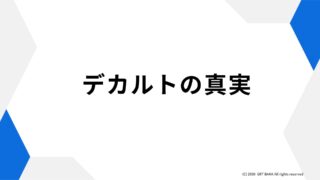



コメント