概要
始めに
今日は松永『ビデオゲームの美学』についてレビューを書いていきます。
ビデオゲームをテーマにする、分析美学入門
この著作はビデオゲームの美学でありますが、広く分析美学の入門書としても有用です。一章はビデオゲームの存在論がメインになっています。二章はビデオゲームの行為論です。三章は芸術哲学、アートワールド論になっています。四章、五章はビデオゲームの言語哲学、言語行為論、行為論です。六章は虚構言語行為論。七章はゲームメカニクスの行為論的分析。八章はハイブリッドな芸術ジャンルであるビデオゲームにおける、異なる意味論(フィクション、ゲームメカニクス)の相互作用について。九章は芸術の空間論、十章は芸術の時間論。十一章はプレイヤーに関する命題のパラドクスをめぐる虚構言語行為論。十二章、二つの意味論の相互作用、再現に関する行為論的分析です。このように、ビデオゲームを通じて、広く分析哲学、分析美学にふれることができます。
初学者には難しい
分析哲学系の書籍全般そうなのですが、手頃な入門書がなく、いきなり個別の文献に当たるのに近い形となるため、初学者には厳しいです。この本も、読んでいて何の話をしているのかわからなくなりやすいと思います。そうした場合は、別の入門書を当たったり、同テーマに特化してついて書かれた入門書を読むと良いのかもです。
例えば『ワードマップ現代形而上学: 分析哲学が問う、人・因果・存在の謎』は存在論の部分で本作の読解の助けになります。
他の芸術ジャンルにも
ビデオゲームはインタラクティブな芸術、ハイブリッドな芸術、複数芸術であり、他のメディアにおける芸術の存在論的考察にも議論を転用できます。
ビデオゲーム史ではない
この著作は行為論中心の記述に関する理論ベースの分析美学的なビデオゲームの研究であって、ビデオゲームの歴史を俯瞰するものではありません。
けれども、空間論に関してはある程度ゲームに触れていないとわかりずらいと思います。
関連文献
・ロバート=ステッカー著 森功次訳『分析美学入門』(勁草書房.2013):美学的再現、虚構言語行為、芸術の存在論について解説。
・戸田山和久『恐怖の哲学 ホラーで人間を読む』(NHK出版.2016):虚構言語行為論について解説。
・『ワードマップ現代形而上学: 分析哲学が問う、人・因果・存在の謎』:分析哲学の入門書ではこれが一番手頃。存在論などは参考になります。

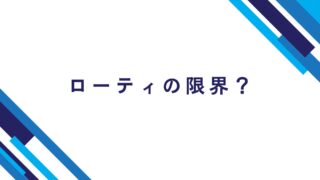







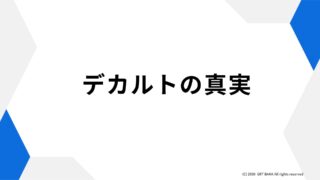




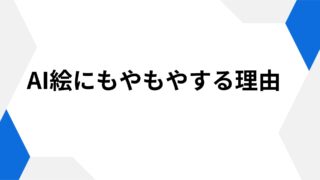

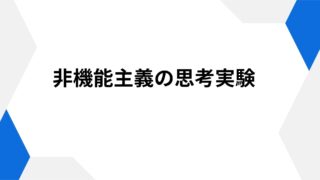

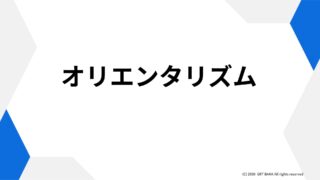



コメント