コンテンツ
サリエリの真実
18世紀末のウィーンで活動したアントニオ=サリエリとヴォルフガング=アマデウス=モーツァルトの関係は、後世で語られるような「天才モーツァルトに嫉妬した凡庸なサリエリ」という単純な構図とはまったく異なります。
実際には、サリエリは当時のウィーン宮廷楽長として確固たる地位を築いた高潔な職業音楽家であり、教育者としても優れた人物でした。彼はベートーヴェン、シューベルト、ツェルニー、リストといった後進を育て、ウィーン楽壇の制度的支柱として尊敬を集めていたのでした。
一方、モーツァルトはその卓越した才能にもかかわらず、社会的経済的には不遇であり、自己評価の不安定さや被害妄想的傾向を示すこともありました。彼が「敵意を持たれている」と感じた背景には、音楽界の派閥抗争や宮廷人脈の複雑さも関係していたものの、サリエリ個人が陰謀に関わった形跡はまったく存在しません。
モーツアルトの神話
にもかかわらず、19世紀以降「モーツァルト=悲劇的天才」「サリエリ=嫉妬する凡人」という神話的構図が生まれ、文化的常識として定着したのです。その起点は、モーツァルトの死後、未亡人コンスタンツェによって行われた「天才モーツァルト」像の意図的なプロモーションにあります。彼女は夫の借金や評判の低下を回復するため、伝記作家たちに協力して、モーツァルトを「誤解され、不遇のうちに早逝した孤高の天才」として再構築したのでした。コンスタンツェが協力したニーメチェクやニッセンの伝記では、モーツァルトの純粋さや感情性が強調され、彼を理解できなかった同時代人たちは「凡俗な社会」あるいは「守旧的な権威」として対比的に描かれました。
この構図は、のちのロマン主義的芸術観と親和的であり、やがて制度的成功を収めた古典主義的作曲家たちは「天才に嫉妬する凡人」として象徴化されるようになりました。
創作への転化
プーシキンが1830年に発表した短い戯曲『モーツァルトとサリエリ』は、まさにそのロマン主義的時代精神の結晶です。プーシキンは史実に基づいた研究をしたわけではなく、既にヨーロッパで広まっていた「天才と嫉妬」の寓話を題材にして、芸術と道徳、才能と正義の葛藤という普遍的テーマを詩的に展開したにすぎないのです。
彼にとってサリエリは実在の人物というよりも、才能を前にして苦悩する凡人の倫理を象徴する装置でした。その後、リムスキー=コルサコフがこの戯曲をもとにオペラ化し、さらに20世紀に入ってピーター=シェーファーの戯曲『アマデウス』(1979)とミロス=フォアマンの同名映画(1984(が登場することで、「サリエリ=嫉妬に狂った凡人」「モーツァルト=神の寵児」という図式は世界的に決定づけられたのです。
しかし史実に照らせば、このイメージはまったくの逆転です。サリエリは高い職業倫理と誠実さを持つ古典主義者であり、モーツァルトに対しても敵意どころか敬意を払っていました。むしろ、モーツァルト自身が精神的に追い詰められ、周囲への不信や孤独感を募らせていたという証言のほうが多いです。
つまり、近代以降に流布した「モーツァルト=孤高の天才」「サリエリ=凡庸な嫉妬者」という構図は、史実ではなく、ロマン主義的天才神話とコンスタンツェの戦略的宣伝の産物であり、プーシキンはその既成の文化的物語を詩的寓話として完成させたにすぎないのです。





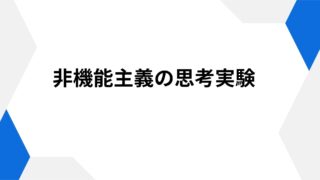
















コメント