コンテンツ
ヒューリスティックとはなにか
「ヒューリスティック」とは、厳密で最適な解法ではなく、経験則や直感に基づいて「とりあえずうまくいきそうな」解決策を素早く見つけるための方法を指します。
完全な合理性や厳密さはなく、最適解を保証しません。実用性重視で、時間や情報が限られていても、ある程度うまく機能します。経験や直感の活用
があり、「こういうときは大体こうすればよい」といった思考の近道です。
心理学では、認知バイアス研究が中心です。カーネマンとトヴェルスキーは、人がしばしばヒューリスティックを使うために体系的な思考の偏り(代表性ヒューリスティック、利用可能性ヒューリスティックなど)が生まれると説明しました。
AIやコンピュータサイエンスでは、チェスや探索アルゴリズムで「完全解析は不可能だから、勝ちやすい手を推測する評価関数」を用います。つまりヒューリスティックとは、不確実で複雑な状況でも、完全解を求めずに“そこそこ良い答え”を手早く導くための工夫です。
認知心理学では、ヒューリスティックは人間の意思決定の仕組みを説明する用語です。「合理的に熟慮する」には時間も計算能力も足りないので、直感的な簡略ルールを使うのだとします。
「思い出しやすいものほど頻繁だろう」と考える(利用可能性ヒューリスティック)、「典型的なイメージに似ていればそのカテゴリーだ」と判断する(代表性ヒューリスティック)などが代表例です。
認知心理学では、バイアスや誤謬を生む要因として分析されます。
計算機のヒューリスティック
計算機におけるヒューリスティックは、探索や最適化アルゴリズムの手法を指します。膨大な計算をしなくても、経験則的な評価関数や近似手法で「そこそこ良い解」を短時間で求めるものです。
例えばチェスAIで「駒の価値の合計」で局面を評価するもの、経路探索で「ゴールまでの直線距離」を優先するものなどがあります。
計算機科学では、むしろ工夫として肯定的な意味合いで使われることが多いです。
ベイズ推論そのものは与えられた証拠に基づいて最も合理的に信念を更新する方法です。しかし現実の問題(探索・認識・意思決定)では、完全な計算は天文学的なコストになります。チェスの完全解析はほぼ不可能だし、複雑な確率モデルの厳密推定も計算不能に近いです。
そこでヒューリスティックは、ベイズ的な理想に近い解を、実用的な時間内で得るための近似として機能するのです。
探索問題では、探索のヒューリスティック関数は期待される残りコストの近似で、ベイズ的な期待値の代替です。モンテカルロ法やサンプリングは厳密な積分や確率計算の近似です。ヒューリスティックなサンプル戦略はベイズ推論を近似的に実装するものといえます。ニューラルネットのハイパーパラメータ探索も、最適化のヒューリスティックです。
二重過程理論
認知科学や行動経済学のヒューリスティックについて見ていきますが、その背景について語っていきます。カーネマンのヒューリスティックはその二重過程理論と結びついています。
二重過程理論について、哲学的直感として、すでに古代ギリシャやデカルト以来、「理性と直感」「理性と情念」という二分法的な発想がありました。1960–70年代の 認知心理学でも、人間の推論・判断に「直感的な処理」と「分析的な処理」の二種類があると観察され始めます。ジョナサン=エヴァンズと キース=スタノヴィッチがこの枠組みを整理して、二重過程理論と呼ぶようになります。カーネマンはそれを踏まえます。
カーネマン&トヴェルスキーは「ヒューリスティックとバイアス」研究を通じて、直感的判断と論理的判断の対比を大量の実証データで示しました。その後、カーネマンは二重過程理論を踏まえ、「システム1/システム2モデル」という形で定式化します。
システム1は直感的・自動的・高速で、努力が少なく、感情や連想に基づくものです。少ない認知的リソースで近似解に至る行動変容プロセスで、原始的な生物はこれに負うところが多いです。もっぱらヒューリスティックはこれに由来するものです。
システム2は、熟慮的・意識的・遅いもので、労力がかかるが、論理や計算を司ります。人間の計算機に固有の、高度の表象推論能力による問題解決システムです。
カーネマンは、人間が複雑な判断をするときにシステム1が「代替」してしまう傾向を重視しました。これを 「ヒューリスティック置換」 と呼びます。
本来問われている難しい質問(例えばこの政治家はどれだけ有能か?)をシステム1が答えやすい別の質問にすり替え(例えばこの政治家はどれだけ好感が持てるか?)、その直感的な答えをそのまま「本来の答え」として使ってしまうというのです。
システム1は普段は非常に効率的で役に立つし、生活の大半はシステム1で動いています。しかし、システム1が作動すると バイアス(偏り) が生まれます。たとえば代表性ヒューリスティック(確率を無視して「似ている」ことで判断する)、利用可能性ヒューリスティック(思い出しやすさを確率と誤解する)は、システム2がチェックして修正すべきなのに、注意を払わないとそのままシステム1の答えを受け入れてしまいやすいです。
行動経済学の理論史的位置
伝統的な主流派経済学では、合理的主体(ホモ・エコノミクス)が完全情報をもち、期待効用に基づいて選好を一貫的に最適化するとします。ただ、実際の人間行動はこれに当てはまらないことが多いです。「合理的期待形成仮説」なども、現実をうまく説明できないケースが頻出します。
基本的に、主流派のモデルは予測のための近似解なのだと言えます。
対して、ポスト・ケインジアンは主流派の「合理的主体」モデルに異議を唱え、不確実性や不合理性を前提に理論を組み立てます。ケインズ的「根源的不確実性」や「アニマルスピリット」など、人間の非合理的行動に注目するのです。
このような前提に由来してポストケインジアンのモデルは構造的次元の記述について説明的、現実適合的、柔軟です。
他方で規範的な予測モデルとしては弱いです。前提にも由来して、合理的期待のように数理的にシャープな予測フレームを提供できなかったのでした。
そうした対立の中、行動経済学(カーネマン & トヴェルスキー以降)は、認知心理学の成果を経済学に導入しました。
そしてヒューリスティックやバイアスを「体系的に」捉えようとします。単なる“不合理”ではなく、有限の認知資源を前提にした合理性の近似形として理解するのです。
つまり行動経済学は主流派の形式性を壊さずに(効用関数・確率モデルを基盤にしつつ)、ポストケインジアン的な人間の逸脱行動を「予測可能なパターン」としてモデル化しようとしたのでした。不合理性を偶然やノイズではなく認知に還元し説明しようとします。
他方で再現性問題(心理学全般の「リプリケーション・クライシス」に巻き込まれる)があり、さまざまなモデルが挑戦を受けています。また、政策的に「ナッジ」などに応用されたが、それも実効性が安定しないという批判あります。
参考文献
・ダニエル=カーネマン『ファスト&スロー』


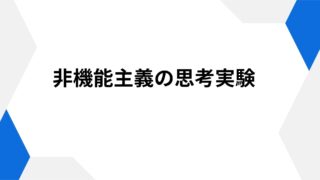
















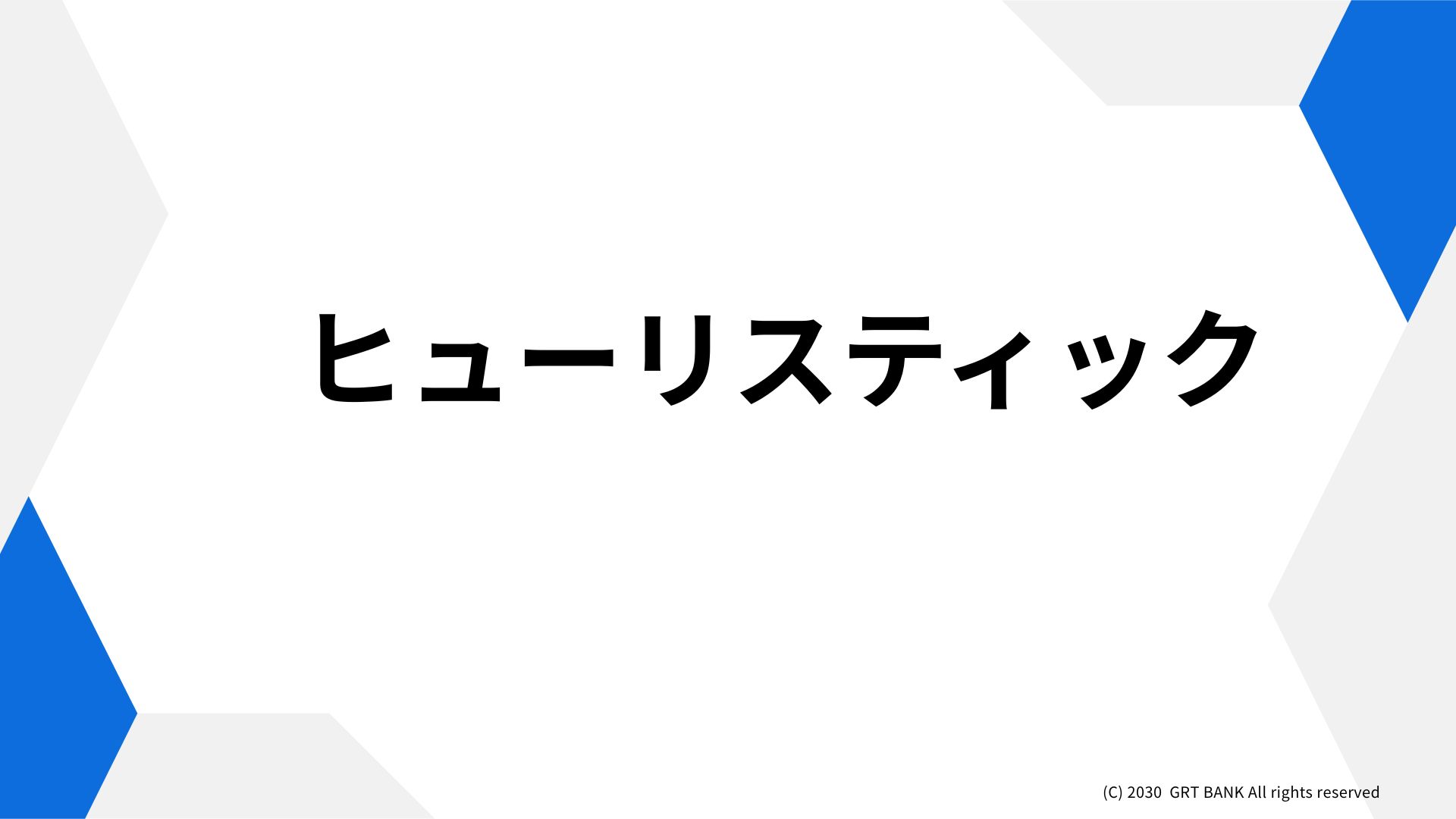


コメント