始めに
今日は備忘録も兼ねて、クワジ実在論の私が非認知主義、反実在論のスタンスから、制度論や美学とのコミットメントの展望について語っていきます。
知人との対話をベースに書き起こしているので訂正がはいります。
コンテンツ
自然主義
私は自然主義といっても、道徳的事実や言明がすべて自然科学に還元できる、という素朴なスタンスでなくて、説明的自然主義、構成的自然主義が主流で、自分は両者をとってます。
説明的自然主義は道徳判断、規範、価値観などの経験的生成過程や社会的・生物的基盤を自然科学(心理学、進化論、認知科学など)で説明する立場ですが、「倫理的なことは自然科学的である」という強い主張ではなく、倫理的判断が人間という自然的存在者の中で生じているという観点に立脚し、進化心理学などとコミットするもの。
構成的自然主義は倫理は人間的実践や制度の中で構成されるものとみなしつつ、その構成過程やその結果の整合性は経験科学との整合性、観察可能性によって支えられる、とするものです。
たとえば動物倫理のレーガン、フランシオンのような非自然主義者が、どうやって経験科学と折り合いをつけているかというと、事実解釈(痛み、意識的苦痛の有無の神経科学的説明)のレベルでは自然科学にコミットしつつ、道徳的カテゴリーに属する真理や事実は経験科学に還元できないものとしています。
形而上学的負荷
ルイスの可能世界論、ネオアリストテレス派、中間実在論、本質主義とか、形而上学的負荷をあまり気にしなかったり説明性を重視する潮流も確かにそこそこあるけど、ただクワイン以降、全体の傾向としては形而上学的負荷を減らそうとする傾向があることはやはり言えると思います。
説明責任、科学との整合性、懐疑論への防衛、不可知論へのリスク、実用性ギャップ、規範的モデルとしての検証可能性へのコミット、前提構造の不明(どの前提が黙示的にどれだけ捨象されているのか不明)などを気にして、形而上学的負荷を全体としてはかなり気にする傾向が強く、それでも気にしない立場もあるけど、さすがに認知主義や実在論もある程度それに応える義理はあるよね、みたいな感じですね。
フレーゲ=ギーチ問題へのクワジ実在論からの応答の冗長性、複雑性も、自然科学に回収されるため、形而上学的負荷も軽度と感じます。
パーフィット、シェファーランダウ的強い認知主義批判
「同意される道徳的直観を見ればかなり普遍的・共通的といえるものも多々あります。」という道徳のコア直観(common core)仮説ですが、直観の一致=客観的道徳的真理の存在とは限りません。また、仮に一部の直観が共有されていたとしても、それは社会的進化や収斂現象としても説明可能であり、実在論的基盤の証明にはならないと思います。
哲学の他領域(論理学や認識論。大陸哲学のような倫理的なものもありますが)は記述的、規則的構造を問題にするものの、倫理学は定言的、行動指向的という点で質的に異なります。なので、「哲学が真理や実在を扱える」について、道具主義者としては、それがどのレベルでという判断が入るのですが、とりあえずそれを受け入れても、哲学と倫理学は定言的、行動指向的な質的違いがあるから、「哲学が真理や実在を扱えるから、倫理学も扱える」というのは、飛躍に感じます。
「直感についてですが、たしかに、形而上学や認識論も直観に依存する局面がありますが、それらは、通常経験的なフィードバックや思考実験による整合性チェックなどで相互に調整される構造があります。それに対し、道徳的直観は往々にして社会的、感情的、文化的に形成され」は、認識論、形而上学の直観(や、広く直感)は、経験的フィードバック、他者との議論、意味論や認知科学との照合を通じて動的に変わりえて、言語ゲームや制度的文脈の中で「調整可能」な性質をもつのに対して、道徳的直観(特に認知主義、実在論的立場におけるもの)は、変化を原則として許さない真理アクセスの手段とされ、経験的説明を認めない部分がある、ということです。
「直観について、道徳的直観だけを切り出して他の哲学的直観と区別できるのかかなり疑問です。」ですが自分はそうでないと思うんですが、仮に区別できないとしたら、道徳的直観にエピステミックな価値を置いて、道徳的真理ドメインへのアクセス、参照と見るランダウ、パーフィットの立場自体が根本から危うくなるのでは、と感じます。またそもそも道徳的直観は、定言的、心理的効果、規範性があるので、いくつかのシグナルにより哲学的直観と形式的に区別できますし、ランダウ、パーフィットの立場なら、両者は本質的にも違うものです。
パーフィット/ランダウ的な非自然主義の基本前提は「1. 道徳的判断には客観的真理がある(道徳的実在論)2. その真理は自然科学的な事実に還元されない(非自然主義)3. 直観はその真理へのアクセス手段であり、単なる心理的な反応ではない」です。そこでは道徳的真理は経験的事実とは別種の実在であり、観察可能でも検証可能でもないとされますが、非自然主義では、道徳的真理は経験的事実とは別種の実在であり、観察可能でも検証可能でもないとされます。パーフィットやランダウも「思考実験や熟慮によって直観を調整する」ことを認めていますが、それは道徳的真理への接近のための理性的プロセスであり、経験的検証や反証ではなく、理性的主体相互の反省的プロセスです。
哲学も観念論、現象学とか直観や直感に重きを置くものもありますが、多くの哲学者(特に分析哲学、自然主義哲学)やほかの経験科学、形式科学にとってそれは議論を始めるための仮定、反例提示や整合性チェックの素材、説明すべき現象で、それがコミットする制度にバイアスを受けていることはありますが、ランダウ、パーフィットにとって直観は普遍的な道徳的真理へのアクセス、参照行為ですから、倫理体系の核となる真理や真理性の根源なので、全然特性が違います。
「人間は真理/事実に辿り着こうとする傾向があり、その真理の一つに道徳的真理も含まれる」はランダウやパーフィットの非認知主義実在論の世界観だと、前提から導かれる帰結とは思いますが、前述のようにその前提自体をうまく説明はできないし、ランダウはEDAみたいな問いにうまく対応できないよね、みたいなことです。
EDAへの反論には信頼性維持説、再調整可能性、道徳的真理の因果的非依存性、知識の実在的前提説、道徳的構造の収斂性仮説などがあるのを知ってますが、基本的に道徳的真理、事実があるという前提自体をうまく根拠付けるものではなくて、実在論の反論の多くは、道徳的真理の存在を前提しそれに整合的な形式を整えているだけで、真理そのものの存在の証明になっていない感じでは。シンガーなんかの再調整可能性、ボイドの道徳的構造の収斂性仮説とかは自然主義にコミットして一応は合理的説明ですが、そのあたりも認知主義や実在論の点でランダウやパーフィットより妥協することでかろうじて成立してる感じです。
また、パーフィット、ランダウの認知主義、実在論も「なぜ規範に従わなくてはいけないのか」をうまく”説明”できているわけではないのでは。というのは、認知主義、実在論の多くは、規範に従わなくてはいけない根拠を、道徳的真理ドメインの存在、それに直観でアクセス可能である理性的存在者としての人間、それに由来する主体相互の反省的実践の蓄積に求めますが、結局前提自体に未知の要素が多すぎて、広く説明的か(説明責任、科学との整合性、懐疑論への防衛、不可知論へのリスク、実用性ギャップ、規範的モデルとしての検証可能性へのコミット、前提構造の明晰さ、などの指標から)というとなんとも言えない気がします。
前提を受け入れれば帰結を受け入れられても、たとえば、キリスト教神学、スーフィズム、カバラとかは神の存在する世界観や不可知論などいくつかの形而上学的前提を所与のものとすれば論理的にほとんど無謬なものも多いですけど、その前提自体が説明に開かれていて広く受け入れられるかというと、微妙ですよね。それをさけるための形而上学的負荷の回避かな、と。コア直観仮説から認知主義実在論を導くように、「世界の民族宗教や宗教で神の存在は同意され、かなり普遍的、共通的な発想だし、直観的にも神の存在は明らか」と言われても、ちょっと受け入れがたいですね。
形而上学的負荷や説明性が全く問題にならないなら、他にプラトンのイデア論とか、フィヒテ、バークリー、シェリングなどのドイツ観念論、論理的に無謬な唯我論も、特に否定する根拠は持ち得ないですよね。
確かにどんな制度にも前提はあるものの、それら前提には質的・量的な差があり、制度的強度・説明可能性・経験的整合性といった基準に照らして選別されねばならず、この意味で形而上学的負荷の回避とは、あらゆる前提の排除ではなく、「制度的に支持されうる最小限で透明な前提の精選」である、というのがCIGへの感慨です。
なぜルールに従うのか
「当然なぜ制度内ルールで規範とされているものに「規範的に」従わなければならないのかという疑問に答えられません。制度内でそうなっているからってだから何だという話です 」、という道徳の定言性とそれになぜ従わなくてはいけないのか、についての説明は、プラグマティズム的擁護(規範が「制度内でそうなっている」というのは、それが我々にとって慣れ親しんだ実践であり、従うことによって相互に予測可能な行動ができるから)、クワジ実在論的擁護(ある規範が制度内で成立しているというのは、それに従うことで他者との期待が成立し、破れば責任を問われるという「社会的事実のネットワーク」を形成している。「それに従うべきだ」というのは、私がその制度のメンバーであるかぎり、他者の期待を無視できないという事実に基づく)、道具主義的擁護(たとえば「契約を守るべき」というのは、制度内で共有されているからではなく、「契約という仕組み」が人々の行動の予測可能性と相互信頼を生むから。つまり規範は道具的合理性に基づいて構成されている)、 行為論的アプローチ(「従う」という行為それ自体が、制度的規範を支えており、規範性はそれに参与することでしか現れない)で応答可能です。
いずれも制度へのコミットメントの合理性により説明するもので、クワジ実在論、道具主義と親和的です。
相対主義と非認知主義
独裁社会はどう評価するか、の例ですが、制度的道徳観=相対主義ではありません。非認知主義の立場や、「制度としての道徳」という言い方はよく相対主義と誤解されたりそれに還元されたりしますが、ここでの「制度」とは単なる恣意的ルールではなく、相互承認、情動的ホーリズム、実践的整合性に基づいた規範構造のことです。
よって不正義な共同体にも道徳体系はある(それなりに整合的な規範体系が存在している)ものの、それとは別のよりよく普遍的な道徳体系(より整合的、合理的、反省的なもの)が可能であり、それを提示するのが道徳批判、改革の実践と、こちらからは言えます。道徳的実践は常に「ある規範体系に従うこと」と「その体系を批判、再構成すること」の両義性を持って、不正義な共同体に属する者が、その共同体の「内部的資源」(例えば共感、誠実、正義という概念)を使って制度を批判することはよくあって、このような批判、変革の営みもまた、制度内的な言語ゲーム的モデルの延長として理解可能です。
真理と非認知主義
「カルトの教祖は死んでいるが、信者は生きていると思い込んでいて、それは事実ではない」という事例から真理についてのこちらのスタンスを提示します。
「カルトの教祖は生きている」という信者の妄想、それによる心理的効用など心的状態は、現象的経験としてのそれの道具的な準実在性までは認めるけど、より洗練された観察モデルに回収されえたり、自然科学的モデルによって洗練された説明に還元されたり、道具的存在者としての説明的安定性や合理性などに由来して、「カルトの教祖は死んだ」という正当化された信念的モデルとは、その準存在者としての強度に違いがあるよねってことです。
またそもそもこの場合の真理ですが、「カルトの教祖は生きている」という観察から正当化可能な信念があったとしても、こうした経験科学一般におけるそれは論理性(数学、論理学のようなトートロジーに裏付けられたもの)による必然的な真理ではなくて、前提条件や観察方法に依存する、偶然的な経験的な真理です。この場合は、思考実験として、世界のなかの事実が固定されていて認識論的不確実性が捨象されていますが、「カルトの教祖が世間で広く死んだと思われていて、それが確からしい説明モデルとされ、信者は生きていると思い込んでいた。しかし、実は警察の捜査やその報告を受けたジャーナリズムが誤解していたために、世間のほうが誤りで、教祖は生きていた」ということも現実では可能性としてはありますよね。
また、分析哲学における、形式科学の論理的必然的な真理や、クリプキやパトナムなどによって提示された規約による必然的真理もクワジ実在論的制度論で説明できます。論理的必然的真理については、「それらの真理は、我々が選び、訓練され、参加している制度(論理体系・記号体系)の内部での必然性であり、制度が変われば真理の形も変わりうる」 、規約による論理的必然的真理は「ある前提体系(規則、記号、語用論的慣習など)の内部で、正当化された信念モデルとしての真理その真理性は、制度へのコミットメント(あるいは制度内実践の合理性)によってのみ保証される」という、準実在論的な道具主義的制度論で説明できます。
それを踏まえて、仮に対応説的に、教祖の死が偶然的経験的真理とするなら、信者らの共同体にも説明のためのモデルはある(それなりに整合的な説明モデルが存在している)ものの、それとは別のより洗練された説明体系(より整合的なもの)が可能であり、信者らのそれを消去、解釈しうる、ということです。
そして道具主義やクワジ実在論は、必然的真理としての倫理的真理、事実ではなくて、前提条件や観察方法に依存する偶然的な経験的でありつつより一貫的、説明的、普遍的な規範倫理モデルを、”真理らしさ”を追求するものとして、倫理学をメタに捉えるスタンスと言えます。
「そのような事例が示唆するところの道具的有用性と真理の関係をどう考えるのかという所です(両者のギャップはある?同一なのか?など)」に答えると、この思考実験では経験科学における認識論的部分が捨象され、量化のドメインの要素(事実)が固定されているので、道具主義的な真理の発想をそのまま当てはめられない、また基本的に”真理らしさ”を制度論的蓄積のなかで志向するのが道具主義、クワジ実在論だから、そもそも正当化された信念モデルが完全に合致する客観的真理の存在自体を前提としない、という感じです。しいて、その思考実験に積極的に応えるなら、そのように「事実が固定されている」こと自体が思考実験的前提である以上、“真理”というものの位置づけもまた制度や観察の枠に依存している(論理的必然性・規約による必然的真理について言ったようなこと)、という形でクワジ実在論や道具主義に開かれている、とも言えます。
認知主義・実在論の立場から見ると「教祖は生きている」という文が真か偽かは、事実に対応しているかどうかで決まり、実際には教祖が死んでいるなら、その命題は偽であり、「準存在」などを持ち出しても、それは真理の問題とは無関係な信念の誤りに過ぎないので、道具的存在者を認めないのはそうでしょう。しかし形而上学的負荷を問題にしない立場なら、特にその存在を否定する根拠も、世界観の不一致以外にはないです。そもそも道具的存在者は自然主義的説明が可能な社会的、心理的現象に、ある種の機能的レッテルを与えているにすぎないので、形而上学的な存在論として構える必要はそもそもあまりないですが。
認知主義、実在論からすると「信念内容として“教祖は生きている”があること」は心理学的、社会学的に説明可能で否定しない。だが、「教祖は生きている」という命題が真であるかどうか、また「教祖という存在が生きているかどうか」は、それとは独立した外的事実によって決まる。」というスタンスになるでしょうが、こちらの道具主義的準実在というのは、ただ信念内容としてあるものにラベルを付けてるくらいのことですよね。
制度論と美学、文芸批評のコミットメント
ギバード的な自然主義のクワジ実在論的制度論を美学、文芸批評とコミットさせたい。そのような制度論からアートワールド論、ジャンル論、読者論(マルクス主義批評、受容理論、ブルームetc)を統合的に再構成したい。
アートワールドにおける「正当な鑑賞」や「文脈的妥当性」「ジャンル内革新」などの言説を、非認知主義的な制度的語用論モデルとして再構成したり、批評言語やジャンル概念ミームの一種として文化進化論とのすり合わせから基礎づけたり、作家・芸術家の戦略的自己モデルを、ミーム進化の中での適応的表現とみなしてジョイス、大江、フォークナーのような制度の歴史的蓄積やサブのアートワールドという制度の衝突のなかで生まれた洗練された表現や作家を考察したり、バフチンのポリフォニーを、制度論的視座をはらむ美学的再現モデルとしてとらえるとか、やりたいことはたくさんある。
「正当な鑑賞」や「文脈的妥当性」は、徳より制度的規範に依存する感じ。行為論と接続するから、行為論的な個々の芸術ジャンル論とも接続が容易。
ミーム論
表象の歴史的展開のプロセスも、ミーム論〜文化進化論のように、ダーウィン進化論から基礎づけることができるだろうけどね。
ミーム(ジャンル、モード、コード、アートワールドetc)に主体があるレベルで行動や選好を決定づけられても、そこにエージェントの主体的、自律的な自由によってミームの決定論を逃れて、独創的かつアートワールドに対する高度な批評性をたたえた表現を展開しうるという解釈とか、芸術史におけるジャンルの対立や衝突のダイナミクスをミームや主体の戦略的コミュニケーションの軍拡競争として捉えるとか。
例えばハロルド=ブルームのモデルなんかもそのような進化的基礎づけができそうだが。
クワジ実在論的美学
クワジ実在論的に美学を捉えると1.美は独立した客観的性質ではなく、態度・実践に依存する。2. それでも我々は美的判断を真偽をもつ命題のように語る。3. その規範性は「普遍的拘束」ではなく「実践的拘束」であり、洗練や共同体的承認を通じて成り立つ。その拘束力にコミットすることは、「美学的再現(表現・批評・鑑賞)の洗練」を可能にし、実践の合理性(よりよい批評やより深い理解)をもたらす。









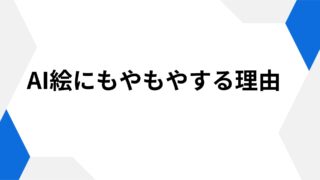






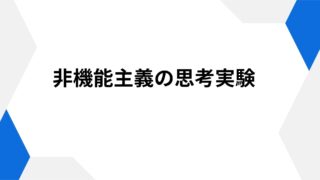





コメント