コンテンツ
マンフレの検討
戦後の主流派国際マクロ経済学は、マンデル=フレミングモデル(IS-LM-BP)を基本枠組みとして、「金利・資本移動・為替レート」の関係を説明してきました。このモデルにおいては、金融政策の効果は”金融緩和 → 名目金利低下 → 資本流出 → 通貨安(円安)”という機序で説明されます。
このメカニズムは、開放経済下でのIS-LMモデルを拡張したもので、資本移動が自由であれば金利裁定が働き、通貨の需給を通じて為替レートが調整される、という構造を前提にしています。しかし、このモデルが機能するのは、次のような古典的条件が満たされるときに限られる。1. 資本移動の自由と裁定の即応性(投資家が国際的に金利差へ反応し、裁定を通じて均衡を保つこと)、2. 短期金利が中央銀行操作によって裁定的に決まる(流動性選好が安定し、貨幣需要が金利に感応的であること)、3. 期待形成が安定しており、金利平価式(UIP)が成立する(為替レートの変動期待が金利差を通じて合理的に決まること)、などです。これらの仮定が崩れたとき、モデルは現実を記述しなくなり1990年代以降の日本はまさにその典型です。
マンフレの問題
まず、ゼロ金利制約(ZLB)は短期金利の裁定的決定を不可能にします。名目金利がゼロ近傍で張り付くと、マネー需要は弾力的になり、中央銀行がいくらベースマネーを供給しても、貸出や支出への波及は起きにくいです。流動性の罠では、「金利操作 → 資本移動 → 為替変化」という伝統的メカニズムが断ち切られます。
さらに、銀行部門が超過準備を抱えた状態では、マネタリーベースの拡大が資産市場全体に波及することもなく、ポートフォリオリバランスも生じにくいぇす。この環境では、金融緩和の効果はもはや金利チャンネルではなく、「期待チャンネル」へと限定されます。
特に日本のように金利差が恒常的にゼロ近傍で推移する国では、為替は金利ではなく「期待・信認・リスク回避」といった心理的・制度的変数に支配されます。したがって、金融緩和が通貨安をもたらすか否かは、もはや実体的条件ではなく、期待の方向性に依存します。
期待が「経済弱体化」「デフレ長期化」へと傾けば、金融緩和でも円高が起こります。実際、2000年代から2010年代にかけて、日本は金融緩和と円高の同時進行を何度も経験しました。これは、世界的なリスク回避局面で「円」が安全資産として買われる構造的要因も重なっています。
ニューケインジアンの応答と課題
ニューケインジアン(NK)モデルは、こうした問題に応答するかのように「期待形成」や「前方視的行動」をモデルに導入しました。しかし、合理的期待を内在化することによって、むしろ現実との乖離を深めています。理由は三つあります。
1に期待の安定性を仮定していることです。経済主体が将来をモデル的に予見し、唯一の均衡を期待するとするものの、実際の期待は不安定かつ自己実現的です。デフレ期待が生まれれば、実質金利が上昇し通貨高が起き、逆にインフレ期待が強まれば通貨安が進みます。現実の為替は、このような複数均衡やレジーム依存性を示すものの、NKは唯一均衡モデルであるため説明できないのです。
2にZLBで金利差が無意味になります。ゼロ金利では、短期金利の差がほとんど存在せず、UIPのメカニズムは凍結します。結果、為替は将来の金利パスの期待に依存するが、その期待は政策信認や地政学的リスクに左右されるため、モデル的に予測不可能となります。
3に制度的信認・政策レジームを扱えないことがあります。NKでは中央銀行や政府が常に「ルールに従って行動」する前提(テイラー=ルール、財政ルール)を置くものの、実際には金融財政レジームが揺らぐ局面こそが為替を動かします。政策信認の変化や制度的シフトをモデル外の「ショック」としてしか扱えない点が、現実的記述力を損なっています。
こうして、金融緩和が通貨高をもたらすという「符号の反転」が現実に生じます。安全資産としての円需要が増すと、金利低下や緩和政策がかえって円高を導くのです。金利上昇が通貨安を招く場合すらあります。これは、リスク選好の変化や国際資産市場のストック的調整によって決まるものであり、短期金利を中心とするNK的均衡理論では記述できないのです。
主流派の限界
総じて言えば、金融緩和 → 通貨安という主流派の定式は、ゼロ金利・流動性罠・期待不安定性の下では成立しないです。貨幣が超過流動性を帯び、期待形成が不安定な環境では、為替はもはや金利裁定でなく、「制度的信認」「安全資産選好」「将来の政策パス」などストック的心理的変数に依存します。
ニューケインジアンは形式的には「期待」を導入したが、それを合理的安定的な形でしか扱わないため、実際の不安定な期待ダイナミクスを説明できないものです。むしろ、ポスト・ケインズ派やストック=フロー一貫モデルのように、金融・財政・信認・期待を制度的相互依存として扱う枠組みこそが、現実の「緩和しても円高になる日本経済」を理解するうえで不可欠です。
要するに、90年代以降の日本経済は、主流派が想定する「金利差裁定の世界」ではなく、期待の不安定性と制度的流動性が支配する“信認経済”へと移行しています。金融緩和が円安か円高かを決めるのは金利ではなく、「経済主体が未来をどのように怖れているか」、すなわち期待の方向性そのものです。

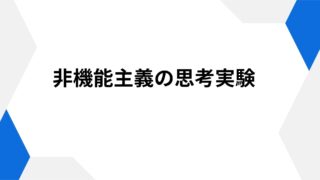










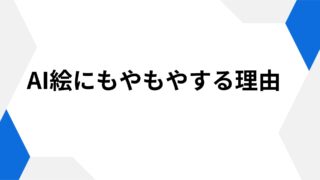









コメント