コンテンツ
マルクスとマルクス主義、現実社会主義国家
マルクスとエンゲルス以降のマルクス主義者は、言っていることの内容や方法がマルクス本人とかなり異なっていて、レヴィ=ストロースとラカンくらいの違いがあります。そのため、マルクス本人の思想と、後のマルクス主義者、あるいはソ連・中国などの現実の社会主義国家の実践、さらには共産主義・社会主義という理念とを分けて捉えないと、話の前提自体が混乱します。
文献学的には、アルチュセールのスピノザ的構造主義などのようなアンチヒューマニズム、制度や歴史による強い決定論的モデルはネガティブに扱われ、サルトルのような観念論的なヒューマニズム的制度論、生の哲学のほうが優勢のはず。アルチュセールは構造主義の理解も恣意的だから、モデルとしてはスピノザに一番負うところが大きいからスピノザ主義哲学・制度論というかんじ。
エンゲルス=レーニン=スターリン主義?
廣松もアルチュセールも、まず現実の関係性の中にある生の主体に立脚する批判的ヘーゲリアンで唯物論者、アンチ形而上学、生の哲学者のマルクスよりも、それをより硬直的・体系的・還元的、観念的なモデルに帰着させるエンゲルス、レーニン、スターリンのラインを継承してて、廣松の場合、唯物理論と物象化論を形而上学・超越論的、ヘーゲル観念論的位相に再構成すること、アルチュセールは現実の関係性のなかにある自律的主体への立脚を放棄して決定論的スピノザ的制度論にそれを帰着させることが、そもそものマルクスの本旨に反していて、マルクス理解としてはそれぞれ文献学的に不適切な、エンゲルス=レーニン=スターリン主義に帰着してる感じ。
物象化を廣松経由で学ぶのは、まずい。 文化的表象への廣松の影響は批評論壇を通じて大きいとは思うけど。
トクヴィル的共和主義とマルクス
他方で、トクヴィルとマルクスは、視点や方向性は大きく異なるものの、現実の人間の実践や制度に立脚して社会を捉えようとする制度論的リアリズムという意味では、ある種の共通点があります。つまり、両者ともに抽象的理念や空理空論に陥るのではなく、具体的な社会の仕組みや慣習の中で人間がどう生きているかを重視するという点では共通しています。
ただしそのうえで、トクヴィルは「自生的秩序」例えば自発的な結社や宗教、中間団体に価値を見出し、個人がそれにコミットすることで自由と自己実現を確保できると考えるのに対し、マルクスは市場や市民社会のような「自律的」な秩序が、実際には階級的支配や疎外の構造を隠蔽、再生産する装置だと見て、階級や資本による疎外や私的所有を排した相互に利他的な共同体の中へのコミットメント、その関係性の網の目なかでの労働による自己実現を目指しました。
したがって、両者が志向する「自由」や「自己実現」のあり方は似ている部分もあるものの、制度の評価や問題設定、そして方法論的な立脚点はかなり異なっている感じ
右派リバタリアニズムと共産主義
右派リバタリアンと共産主義は、確かに政府をネガティブに見る点やそれぞれの定義における労働(ここも内実は全く異なり形式的な一致に過ぎない部分)による自己実現を志向する点で重なるものの、根本的に根ざす理念が違うから、表裏一体みたいなレトリックも好きではないな。
リバタリアンは契約的自由と所有権に根ざす交換の実践のなかでの市場の秩序と正義に、共産主義は階級や格差のない共同体における相互に利他的な関係性の網の目のなかでの実践(私的所有の廃止と共有、共愛)規範とする制度論に根ざし、共に国家などによる干渉や支配をネガティブに捉えるけど、リバタリアンの場合は市場を最適な秩序をもたらす制度とみるから、富の偏りや資本による契約的自由と所有権への抑圧は長期的に実践の中でならされうると見る点で私的な権力にかなり楽観的だったりそれを正当化可能として問題にしなかったりで、国家の廃絶までは概してめざさない。共産主義はそうではないと見て国家の廃絶に加えて、資本による搾取をネガティブに捉える。
形式的に共通していても本質的に全く異なるものだと思う
労働価値説はトンデモ?
マルクスが追求したのは、価格の短期的メカニズムというより価値という社会的、歴史的構造。
確かにマルクスは、需給との関連については考察しつつ、短期的な価格決定のメカニズムについて十分な説明を理論的に展開しなかったけど、もっぱら長期的な価格傾向と価値に根ざす生産価格、市場価格の関係、また利潤率、資本集中、搾取構造についてモデルとしたもので、需要関数で否定されるものでもない。
長期的価格傾向や資本による制度的メカニズムについて、数理マルクスは数理実証モデルで基礎付けようとしたけどあんまりうまくいかなかったよ、な感じで、分析的マルクスだとマルクスの制度論的発想を重視して、労働価値説の問題意識をそこから再構成する感じ。
とはいえ流石に数理マルクスよりは、批判的にマルクス的発想を数理実証モデルにより基礎づける点でピケティのほうが上手くいってるとは思う。
でも、モデルとしてマルクスを救うなら疎外論を制度論から基礎づける分析的マルクス的ベクトルが望ましいだろうし、そこから労働価値説も再定義する形で説明し得るとは思う。
数理マルクス、分析的マルクス
分析的マルクスと数理モデルの関係ですが、分析的マルクスはマルクスの理論を現代的な分析哲学や社会科学の方法で明確化するもので、ゲーム理論や形式モデルを使う場合もありますが、必須ではありません。主流派経済学や数理モデルにもかならずしも依拠せず、むしろ不確実性についてポストケインジアンぽい前提をとることも多いです。分析には歴史的資料や制度分析を用いることもあり、純粋に数理モデルに依存するわけではありません。
数理マルクスは、主流派の数理実証モデルベースです。
傾向としてマルクスは数理マルクス的な数理実証モデル(合理的選択理論・均衡モデルなど、予測的近似値モデル)での還元的説明を、(アンチ形而上学として現実の生の主体に立脚する)前提や記述対象・関心の相違(主流派は規範的議論のための予測的な近似値。マルクスの記述対象は疎外という現実の事態のメカニズム)に由来して強いレベルでは拒む傾向があるので、分析的マルクスの方がマルクスを批判的に継承、再構成するアプローチがやりやすいです。
エルスターの合理的選択理論も、主流派のそれよりポストケインジアンに近い設定です。限定合理性を強調し、主流派のような完全合理性ではなく、「人間は不確実性や制約の中で行動する」という前提を敷きます。また予測的均衡点を描くよりも、「どういう因果メカニズムで結果が生じるか」を重視します。市場だけでなく、社会制度や歴史的背景を行動説明に組み込む制度論はポスト・ケインジアン的です。選好や欲求の「形成」や「妥当性」にまで踏み込み、単なる効用最大化の枠で還元的に理論的モデルとしません。主流派経済学より制度論的社会科学的モデルです。
数理マルクス、分析的マルクスと労働価値説
マルクスにとって労働価値説は”価格”を説明する理論ではなく、その本源である”価値”によって、資本主義における社会的関係の物象化・搾取の仕組みを可視化する理論なんですね。
労働者は自らの労働によって価値を生み出すが、その一部(剰余価値)は資本家に帰属し、この構造が搾取の理論的基礎であり、単なる市場価格の差異ではなく労働過程そのもののあり方に根ざす。さらに、労働が自分自身の自由な自己実現ではなく、外部の利益のために従属させられるとき、それは疎外として経験される、という感じです。
それで数理マルクスや分析的マルクスはそれぞれ疎外や搾取について、こんにちてき分析的枠組みからマルクスやマルクス主義を洗練させることで再定義・実証しようとして、とくに搾取については重視されやすいです。
数理も労働価値説はかなり捨ててるんですが、基本的に主流派的数理モデルによる形式化をマルクス主義経済学に適応しようとするもので、それが結構無理があって、限定的な射程でしかマルクスの批評意識に接続できなくて、結局搾取や疎外の構造的な分析を継承・洗練するよりも、その限定的な側面や発想を部分的に実証的に確かめるくらいのことになっている感じです。
コーエンの後期のそれは、マルクスを正義、権利論から整理して疎外や搾取を労働者の所有権の侵害としてとるのですが、マルクス自身は”(もっぱら生産手段の)私的所有の廃止”が知られるように、所有権に強く立脚してないことはテクストから明白なんで、筋の悪い整理で別の規範体系になっていると。
エルスターとかローマーも搾取について制度論的に翻訳していて、ローマーは一般均衡理論を用い、搾取を「資源分配の非対称性」から定義していて、労働価値説に依存しない搾取概念を提示するものの、労働の疎外や価値生成プロセスを説明しません。エルスターは合理的選択論を援用し、マルクスを制度論、メカニズム論的に翻訳し、搾取や疎外を「制度的メカニズムによる不自由」と捉え直します。
ローマーもエルスターも、あるレベルで労働価値説の批判的射程を継承してるとも言えますが、とはいえその本質としての”労働による価値からの搾取、疎外の生成メカニズム”について語ってはいないので、かなりオミットされてはいます。
他方で、マルクスに於いても中心的な興味は現実の生の主体とそれが関係性のなかで直面する疎外の構造的分析とその克服なんで、労働価値説自体が内在的に代替、再構成不可能かというとそうとも言い切れず、分析的マルクスのそうした態度へも評価は分かれうるし、その点でエルスターが分析的マルクスでは比較的筋がいい、くらいの感じです。
共産主義と資本主義、どっちがただしい?
「資本主義と共産主義どっちが正しいか」「共産主義は正しいが実現不能だから資本主義が理想」みたいな言説をしばしば見るけど、「資本主義」ってもともと社会主義思想の方面から、既存の経済的実践のはらむ不正義に対する認識論的枠組みとして提起されたものだから、そもそもそれを肯定的に捉えるのは難しいし、それはどちらが正しいかと言ったらまあ共産主義になるとは思う。
他方で、共産主義を目指した現実社会主義国家群が実現したのは、マルクスの糾弾した資本主義と変わりない抑圧的コミュニティで国家資本主義のバリエーションめいたもので、そうした国家群が資本主義勢力として対峙した西側の自由主義国家から学ぶべきところは大きかった気がする。
また、マルクスの空想的社会主義であるところの共産主義を現実社会主義の全体主義や経済的破綻、不効率の所以みたいに見て「人類には共産主義は無理」というのも、マルクスと以降のマルクス主義者の言説では相当に開きがあるから無理があるとは思う。
「資本主義と共産主義どっちが正しいか」ってのがなんかおかしいのは、結局「資本主義」は具体的な制度や制度の構想というか、古典的自由主義などに裏付けられた伝統的な社会経済的実践がはらむ不正義に対する社会主義思想からのモデル化が資本主義で、マルクスも共産主義も具体的な制度であるよりも、まずそれまでの空想的社会主義と相対的にはより科学に立脚したユートピア社会の方向性の理念、理想だからかな。
弁証法
まずマルクスとエンゲルス以降のマルクス主義者は主張がだいぶ違っていて、”マルクスが言ってないから誤謬、理論的に不適切”は言えないと思う一方、マルクスとは似て非なるエンゲルス以降の教条主義的マルクス主義や弁証法的唯物論はソ連や中国など現実社会主義国家の暴走の理論的根拠や方便になった側面が歴史的に強く、実際それはかなりその理論的帰結だと思うので、左派としては警戒的になるべきなのかなと思います。
弁証法に関しても、マルクスの唯物論はヘーゲルの形而上学への批判的参照なので、現実の主体や生産関係のダイナミズムをそれで捉えようとするものの、普遍性、必然性などにおける強い形而上学的負荷をオミットしています。またあくまでマルクスの歴史はオンタイムの実証レベルでの合理的正当化なので、唯物論的弁証法で正当化される強い法則性までマルクスがそこに認めていたか微妙で、後世に法則性が誇張された部分があります。エンゲルス以降のマルクス主義では唯物史観の弁証法的必然性が強調され、それが教条主義的ドグマとして機能していった経緯があります。
コーエンは、前期にはそのようなエンゲルス以降のマルクス主義を前提に、弁証法的なダイナミクスを体系化する路線で分析的マルクスを展開している感じで、分析的マルクスは必ずしも弁証法を捨て去ったのでもありません。他方、確かに制度論的次元でエルスターなどのようにほかのモデルに依拠し、それをオミット、再構成する傾向は強いです。
労働価値説はほとんどの論者のモデルでオミットか部分的に再構成されています。
今はブランダムやマクダウェル(後者はハイデガーベースですが)のようなヘーゲルを規範などの歴史的実践の構造的モデルとして参照する哲学者もいるので、分析的マルクスもそういう方面から今後弁証法を参照していくべきなのかもしれませんね。
また、主体や権利、責任、自由意志の再構築や再定義に興味があるなら、デネットやミリカンらセラーズ右派の発想が、そのような関心から分析的マルクスの制度論と接続可能かもしれません。戸田山『哲学入門』が、デネットやミリカンの入門書として優れます。
所有権と疎外、搾取
コーエンの、疎外や搾取を権利論から捉える解釈は不適切です。
労働の疎外は労働それ自体の在り方から説明されます。労働者の生産物は自分のものにならず、外部の力(資本)に従属します。すると労働過程そのものが、自己実現の活動(労働)ではなく「生存のための苦役」と化します。こうして他人(資本家)や自然、同じ労働者との関係も疎外される。所有権が形式的にどう規定されていても、労働が自己のものではない力に支配されている限り、疎外は生じるのです。そこでは労働の在り方そのものから疎外が説明され、また所有関係は労働の在り方を制度化し、再生産するものです。
労働の成果が自分に帰属せず、”労働が資本の自己増殖のための手段として編成されること”が疎外のメカニズムです。
搾取は「資本家が剰余労働を収奪する」こと(労働価値説)です。所有権の有無よりも、労働力の商品化(労働者が労働力を市場で売るしかない状況)が基盤です。労働力は「労働者の再生産に必要な価値」で取引されるものの、実際の労働過程でそれ以上の価値を生み出します。その差が「剰余価値」であり、資本による搾取です。形式的には「自由で対等な交換」でも、労働過程そのものの構造によって搾取が発生します。
所有権について考えると、まずマルクスにとって疎外とは、人間の活動や生産物が自分のものではなく、外部の力として立ち現れることです。資本主義における所有権は、”生産物や生産手段が労働者のものではなく資本家のもの”という社会関係を法的に定式化したもの。つまり、労働の外化、他者による占有、法的形式としての所有権という流れです。この意味で、所有権はすでに成立した疎外の社会的・法的形態で、後期コーエンが捉えるようにマルクス自身は労働者の所有権、自然権から疎外や搾取を捉えたのでないことは明白です。
なので疎外論、搾取のマルクス的説明はヒューマニズム的直観に根ざす、というよりは、現実の構造分析から説明されるものです。
マルクスの倫理的位相
マルクスの倫理的スタンスを整理すると、まずメタ倫理の次元では クワジ実在論 に近い立場、とりわけギバード的な自然主義的クワジ実在論 に近いといえます。つまり、道徳的価値を形而上学的に自立させるのではなく、社会的実践に内在させながら、単なる主観的投影ではない拘束力を認める立場です。
規範倫理の次元では、マルクスはカント倫理学や功利主義のような伝統的規範倫理に対抗する方向性を持ちます。そのベクトルはケアの倫理 やポスト構造主義フェミニズム と類比でき、関係性や構造への批判的感受性という点で近い。ただしマルクスはこれらと異なり、相対主義的な認識論や真理論には立たず、歴史的唯物論というフレームワークを保持し続けます。
この点でマルクスの立場は、相対主義でも絶対主義でもなく、「歴史的・社会的に条件づけられながらも、実践に拘束される客観性を認める準実在論」 として理解できます。
方向性としてはマルクスは広義の徳倫理的な感じです。でも批判的ヘーゲリアンとして徳のような形而上学的実在や抽象的人間本性によらない、徳倫理的な、現実の人間主体の解放の規範というか。
空想的社会主義と科学的社会主義?
”空想的社会主義”とされるものの中には実際フーリエみたいに神秘主義的空想的であって経験科学的、科学的でないものもあるけど、オーウェンとかそうでもないし、サンシモンは社会主義なのか微妙だけど神秘主義の影響こそあれども経験科学に立脚しようとするものだし、必ずしも”空想的/科学的社会主義”って分類的に適切な区分でなくて連続性大きいもので、レッテル自体にエンゲルスによる自己プレゼンの意味合いが強いとは思います。
正直、エンゲルス以降の法則的真理をそこに認める唯物史観論とか弁証法的唯物論とか、そもそもエンゲルスが批判しようとしたような意味で空想的でもあります。
ラスキンとかも、空想的社会主義の系譜に連なるのかもしれないし、科学に強く立脚したわけではないけど、プラグマティズム的制度論的な社会主義思想として、マルクスと重なるような形で抽象化、モデルの練度高かったりするし、あんまり有効なレッテルなのかわからないです。
マルクスの労働とはなにか
マルクスの言う”労働”は主体が社会的存在として自己を媒介に社会や自然に関与する活動全般を指すもので、余暇とか政治参加も含んでいて、搾取に特徴づけられる資本主義に典型的にそれがどのように主体が疎外された形で展開されるのか考察したものだから、一般的な意味での賃労働と意味が違うので、そういう存在論的含意を捨象して経済的カテゴリーに還元する形で労働を解釈していったのはエンゲルス以降です。
アレントは人間の実践を1. 生存維持のための反復的行為(労働)2. 目的的制作=人工物の創造(仕事)3. 他者との間の自由で公共的な実践(行為)に分類してマルクスが1の労働にばかり焦点を置いたとか言ってるけど、全部マルクスのいう”労働”です。マルクスの”労働”は”社会的な創造的活動”のことなんだから、別にマルクスは”勤労の美徳”や”公正な賃労働の称揚”みたいな話は全くしてなくて、賃労働は疎外された労働の一形態です。
宗教
マルクスは宗教について、レーニンとかマルクス主義者のように教条主義的にそれと対立的に構えてなくて、フォイエルバッハの批判を踏まえつつ、”暴力革命”と一緒でそれを疎外におかれた主体の社会的症状と見てる感じで、確かにそれが疎外を再生産する構造があるとは見ていたけど、そもそも共産主義が成立されば自然消滅すると思ってたから強く対立的に構えていません。宗教の来世志向が現世の問題や現実に目を背けさせ疎外の契機になるとは思っていたけど、階級の消滅で自然消滅するってのが前提です。
『ゴータ綱領批判』も、形而上学的な宗教的ドグマによる統治やイデオロギーの搾取への批判は見えるけど、強く宗教的感情自体を否定しないし、それに理解を示し、構造的な問題を解消することで自然消滅させるものです。
マルクスは宗教を疎外に置かれた主体の社会的症状と見たけど、実際はそうではなくて宗教が社会的関係のなかでの主体の労働の価値と不可分のものとしてあって、超越論的なものや崇高なものへの畏怖や共鳴が疎外を伴わない形で再構成されるものであるのなら、共産主義と両立しうるようなものです。
マルクスの資本主義評価
マルクスは実際は資本とか市場経済のポジティブな側面にも着目して階級闘争の歴史のなかで暴力革命同様に相応に積極的に評価したうえで、そこで搾取や疎外が起こる社会的条件を問うて批判的に克服しようとした感じです。だから資本主義が成熟して(内在的矛盾が止揚されて)プロレタリアの革命から共産主義にいたるってことになります。
資本主義を破壊して別のものを持ち込むというより、むしろ資本主義の内的運動そのものが自己変革していく方向を理論的に描いてそれが共産主義という新しい社会的関係に転化する道筋を描こうとしたもので、だから”資本主義を肯定し過ぎでは?”って昔から言われることです。ブルジョワや、フランス革命などのブルジョワ革命の階級闘争の歴史のなかでの役割も肯定的に認めています。
暴力
マルクスの暴力革命論は時期によって(歴史的条件に依存して)一寸違うけど、フランス革命などの暴力革命は歴史的な因果として一定の評価をするけども現実の規範的処方箋としては条件付きで肯定するけど不可欠ではなくて後期になると英米の議会政治にも肯定的くらいの立場で、でも共産主義の理想に暴力や暴力革命は不可分でないと思うし後続がそれを推奨するべきだとも思えないです。
1848年の『共産党宣言』のときは、歴史的条件に依存して暴力革命についてそういう評価になったけど、例えば今でもベネズエラとかが何のgewaltも伴わずに抑圧から解放しうるとは現実的に想定できないけど、あくまでマルクスはそういう社会的条件の存在とそこでの暴力革命を因果として認めて積極的に評価しただけで、一般に暴力を強く奨励するのでもありません。


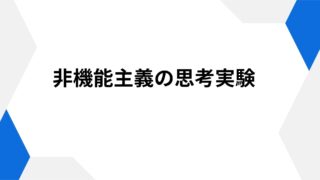



















コメント