コンテンツ
カントとヒューム的懐疑
認識論的懐疑はデカルト以降の基調だけど、カントの認識論的世界観はロックを踏まえつつ表象と客観的世界の非対応を深刻に受け止めるヒュームを強く継承するものです。
カントにおける「物自体」とは 私たちの認識の形式(時間・空間・カテゴリー)を超えた、認識以前に存在するものそのものです。経験される以前の、対象のありのままの存在で、「我々が知覚し、概念化した“対象”ではなく、知覚や概念化の背後にある、独立した実在です。
カントによれば、私たちの認識はつねに時間・空間という感性のアプリオリ形式と、因果・数量などの悟性のアプリオリ概念(カテゴリー)を通して成立します。私たちが経験できるのは、すべてそのアプリオリ形式によって構成された現象で、それを離れた物自体は原理的に認識不可能です。物自体は存在する(思惟されうる)ものの、しかしそれを経験的にも理論的にも把握することはできないとします。
アプリオリはわれわれの心の側に属する。経験を可能にする「認識の形式」で、物自体はその認識形式の「外側」にある、認識以前の実在です。アプリオリは、物自体を直接知るための手段ではなく、物自体が私たちに現象として現れる仕方を構成する枠組みです。現象はアプリオリな形式(時間・空間・カテゴリー)を通して構成された「経験可能な世界」といえます。
物自体の経験不可能性
物自体が経験不能なのは、感性と悟性の統一的作用に依存する経験という行為がそもそも「時空」(感性について)と「カテゴリー」(悟性について)という認識的構成プロセスの形式に依存するものだから、物自体はその認識の前提となる形式の外に存在するから、形式に制約される認識に内在してそれを経験不能って感じです。
経験とは構成的プロセスで、その前提となる形式を超えたもの(=物自体)は経験されえないから、動物とかAIとかほかの観察、認識主体があっても個々の認識形式に内在して構成される現象界があるだけで、物自体を直接経験することは難しそうです。認識されうる、知りうるものは認識的プロセスによって再構成されているから、世界の客観的なアプリオリな秩序の前提たる物自体を記述することはできない(しようとしても形式に依存して構成される知識として間接的に記述されるだけ)し、認識の形式的限界から直接経験もできません。
カントからすると「人間が時間・空間をもたないものを思考できないから物自体を経験できない」というよりは「感性の形式としての”時間””空間”を前提としないものは経験的認識の対象として成立しえない」というかんじで、時間や空間から切り離された対象は思考可能かもしれないけど、認識論的フレームである感性の形式としての”時間”や”空間”に依存せず経験できない物自体は認識に内在して経験不能で、現象として立ち現れないから知覚不能です。
理性から物自体や時間や空間を欠く対象について思考はできるだろうし、そうでないとカントの哲学自体成り立たないです。理性の働きにおいて、時間・空間を欠いたものや物自体を思考することはできるけど、その思考は経験的認識ではなく、経験の限界を示すための境界的思考です。
物自体=世界そのもの?
”物自体=世界そのもの”ではありません。
世界を構成する個々の対象の、経験に先立つ超越論的存在様式が物自体で、その超越論的な媒介項があるために、経験的に”世界そのもの”を確かめられないという感じです。
物自体は”世界そのもの”というよりは、プラトンの”イデア”やヘーゲルの”本質”みたいな現象の背後にある構造だけど、イデアや本質と違って現れたり接近できたことを確かめることはできなくて、それゆえに認識論の限界と不確実性の根拠となるものです。
なのでセラーズとカントの主張は結構違います。セラーズとカントはいずれも「与えられるものがそのまま知識を保証する」という素朴経験主義を批判している点では共通するものの、セラーズは、信念や表象の操作は社会的・歴史的な規範のネットワークの中でしか成立しないとし、経験的「与件」は神話であると批判します。一方カントは、人間の認識が感性と悟性という先天的形式に制約されているため、物自体を経験することはできないとします。前者が言語的社会的構成を問題にするのに対し、後者は超越論的構造を問題に認識論の限界を設定します。
セラーズの場合認識論的実践は認知と環境としての実践的ネットワークの相互依存的作用として現れるものだから、知識や信念は歴史的に構成された体系のうえに成立するから”剥き出しの事実”や”対象そのもの”は経験的に与えられないということだけど、カントはそういうことではなくて、もともと認識論的実践において認知が前提とする形式があってその外にある物自体は経験不能で、”対象のありのまま”は物自体という前提の経験不可能性から原理的に確かめられないということです。
科学哲学の真理論、知識テーゼ
「客観的世界に独立した秩序があったとしても、獲得される真理は経験可能な世界において認識の形式・実践の枠組みによって構成され、秩序と記述は直接対応しない」というカント的直感は、ハッキング・パトナム・デネットらの実践的・構成主義的実在論に共通する土台だけど、客観的世界と表象の断絶は超越的媒介項としての物自体を経験の前提にはさむカントほど設定されないし、認識論的懐疑の程度も抑えて関係的連続性が強調される感じです。
デネット、ハッキング的実践的実在論でもカント同様に、対応説的に「世界そのもの」を知ることはできないとし、しかし人間の実践(経験・操作・行為)を成り立たせる外部的現実を前提します。その外部は表象の対象ではなく実践的関与の前提として現前し、カントはこれを「物自体」と呼び、ハッキングは「介入可能な実在」として扱い、デネットは「機能的・行為的実在」として語る感じです。
他方、カントでは「理論的不可知性」が認識の形式からアプリオリに導かれるのに対し、ハッキングやデネットでは「不可知性」は認識論的不確実性に依存する科学的実践の限界や操作主義的枠組みの反映で、カントは超越論的レベル(認識そのものの条件)で物自体を設定するのに対して、ハッキング、デネットは実践の内的構造で実在を前提していて、科学的実在は経験的に対応説的に記述できていること(強い知識テーゼ)は確かめられないものの、経験的に確かめられる範囲で実在を信頼できる形で記述していることが認識論的合理性に内在して言えるので、そのレベルでは実在を確かめられます。
カントの場合、独立性テーゼは満たすけど知識テーゼは物自体という限界に由来して満たさないから、対応説的な強い科学的実在論は取れません。フラーセンとかと近くて、実践的実在論よりも知識テーゼは弱いです。
しかしカントはフラーセンよりも知識テーゼへの留保が強いです。フラーセンにおいても、理論的構成を超えた物自体的な次元は想定されうるけど、超越論的な限界概念として強く要請されるわけではないし、それを経験的十分性の範囲外に置くだけで、理論的に不可避な前提とはされないからです。
クワインの批判以降
カントの真理論はヒュームへの応答です。
ヒュームは、人間の知識がすべて感覚経験に由来するという立場から、因果関係や必然性といった概念も実際には経験の中で観察される「習慣的連合」にすぎず、理性によって保証されるものではないと論じました。これによって、自然法則や科学的認識の基礎を脅かす深い懐疑が生じます。
カントはこのヒューム的懐疑に衝撃を受け、知識の源泉を経験の集積にではなく、経験を可能にする主観的構成条件(感性と悟性の統合的作用)に求めます。われわれが経験を通じて世界を認識できるのは、感覚データを時空間や因果性といった先天的形式のもとで統合する能力が人間に備わっているからだとしたのでした。
つまりカントは真理の強度や成立条件を経験を可能にする感性と悟性の統合的作用を規定するそれぞれの形式のうちに、認識論的基盤のうちに求めたといえます。
アプリオリ/アポステリオリな真理は物自体を前提に、悟性と感性による認識論的形式に依存して成立する形式的/経験的真理の強度に階層を与えようとするものです。
ただクワインの形式科学も認識論的実践と経験に開かれている旨の批判は有力で、カントの区分は真理の強度の指標としては素朴には支持されず、例えばパトナム的に認識論的合理性と不確実性の基盤に内在しつつそれを規約主義と折衷された次元で真理の強度を考えたり、クリプキの可能世界論のような形而上学的発想から必然性を再構成されるような感じです。








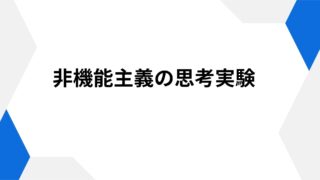







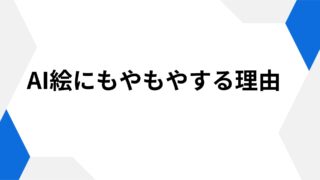





コメント