コンテンツ
新カント学派
新カント学派とは、十九世紀後半から二十世紀初頭にかけてドイツを中心に展開した哲学運動であり、カントの批判哲学を近代科学や文化の状況に即して再解釈しようとしたものです。
ヘーゲル以降の観念論が衰退し、自然科学の発展とともに実証主義的世界観が支配的になるなかで、新カント学派は、科学的知識の正当性を認識論的に基礎づけ、形而上学的実在論に陥ることなく、経験を可能にする普遍的原理を明らかにしようとしました。
この学派は大きくマールブルク学派とバーデン学派の二潮流に分かれます。マールブルク学派(ヘルマン=コーエン、パウル=ナトルプ、エルンスト=カッシーラーら)は、自然科学の認識論を中心的課題とし、認識を経験的与件から出発するものではなく、理性の構成的活動によって成立するものとみなしました。彼らにとって哲学とは、科学的認識がいかにして客観性を獲得しうるかを明らかにする思考の論理で、世界の実在的基礎を問う形而上学ではありませんでした。カッシーラーはさらに科学のみならず芸術・言語・神話など多様な領域を、象徴的な意味形成の体系として捉える象徴形式の哲学を展開したのでした。
バーデン学派(ヴィルヘルム=ヴィンデルバント、ハインリヒ=リッケルト、マックス=ヴェーバーら)は、文化科学の方法論を主題とし、自然科学と文化科学の区別を対象の性質ではなく認識の方法に求めました。自然科学は法則を定立するのに対し、文化科学は個別的・価値的な意味を理解します。この区別を通じて彼らは、哲学を存在の学ではなく価値の学として構想し、科学的認識の背後にある価値関係を批判的に考察する立場を打ち立てました。ヴェーバーの「価値自由」や「理念型」の方法論はこの系譜に連なっています。
新カント学派は、実証主義と形而上学の双方を退け、批判的認識論に立脚して科学や文化の合理的基礎を探求した点で、近代哲学の一つの到達点を示したといえます。しかし第一次世界大戦後になると、その形式的・方法論的性格が批判され、現象学や実存哲学、歴史主義などにスタンスを奪われます。
カントの遺産とバーデン学派
カントはヒューム的懐疑に対して、経験の可能性の条件を問う超越論的観点から、アプリオリな形式とアポステリオリな経験の統合による内在的認識論的世界観を構築し、これを通じて経験的実在論を確立しました。そこでは超越論的な物自体を限界項として設定しつつ、形式科学から経験科学へと真理の強度のグラデーションを描くことで、科学的実践の合理性を保証します。
新カント派は、この構想を継承しつつ、アプリオリを歴史的・文化的に形成されるものとして再解釈し、そのうちのバーデン学派は超越論的な価値関係を社会科学の構成的条件として位置づけることで、社会科学を自然科学とは異なる固有のアプリオリ的合理性をもつ実践として基礎づけました。そのなかから理論的直感を批判的に継承しつつ近現代の実証的社会科学につながるヴェーバー(リッケルトの弟子)が出てきます。
バーデン学派の「価値関係」は、カントの「物自体」を外部から内部へと内在化する点で、ヘーゲルの「本質」概念に構造的に近いものの、ヘーゲルのように全体的体系へと展開せず、文化的意味づけの条件として留めるものです。





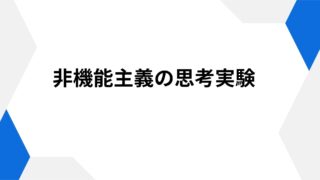
















コメント