コンテンツ
カントの真理論。アプリオリ
アリストテレス以降の伝統的定義は「真理とは、知性と対象の一致である」、です。
カントも『純粋理性批判』でこの定義に触れます。しかし「思考が対象と一致しているか」を直接比較することはできません。というのも、対象そのもの(物自体 Ding an sich)には到達できず、われわれが認識できるのは現象に限られるからです。したがって、従来の「一致説」だけでは、認識が真かどうかを判断する基準が欠けていることになります。
カントによれば、真理は「判断が対象に合致すること」ですが、その基準を外に(物自体に)求めることはできません。そこで彼は「認識能力の先天的形式(悟性の範疇や感性の直観形式)に即して対象が構成される」という構造を持ち出します。つまり、対象と認識が一致するかどうかは、私たちの認識能力が定める一般的な規則(悟性のカテゴリー、統覚の統一など)に照らして判断されます。
形式論理(矛盾律・同一律など)は「思考の正しさ」を保証しても、「真理そのもの(対象への合致)」は保証しないため、真理の基準は、われわれの認識能力のアプリオリな構造(直観形式+カテゴリー) に求められるとするのです。
つまり真理=判断と対象の一致ですが、「対象」は アプリオリな認識形式によって規定された現象 に限ります。よって、真理基準はアプリオリな構造そのものです。アプリオリな真理(総合的アプリオリ) は、この構造から導かれる「普遍必然的に正しい判断」で、経験的偶然性に依存しません。
総合と分析、アプリオリとアポステリオリ
分析的/総合的は述語論理の内容にかかる意味論的、アプリオリ/アポステリオリは認識論的区分、分析的判断は主語概念のうちに述語概念が含まれている判断で、定義や集合の論理的関係によって成立する恒真命題、総合的判断は主語概念のうちに述語概念が含まれておらず認識を付け加える判断です。
カントにとってたとえば「1+1=2」がアプリオリな総合的判断なのは、経験に依存せずにそれが成り立っても、命題を構成する要素の概念分析(量化のドメイン・意味論的定義特定)だけではそれが確かめられないから、分析的ではなく総合的としました。こんにちからすると公理系に依存してそれが定義展開として分析的に成り立つ気もするものの、当時の数学はまだ論理的に体系化されてなかったので、オンタイムの数学を前提にそれを、概念分析だけでは導けずに時間的直観を媒介的に要する総合的アプリオリとカントはみました。
分析的というとなんとなく形式的・論理的と聞こえるけど、カントのそれは分析哲学的な概念分析としての分析。
今日からすると「1+1=2」はペアノ算術の公理系や定義から定義展開として導かれるから分析的に近いものの、他方で成立を理解するためには公理系のメタ的構造(形式的体系)という前提的な構成の把握を要するから経験に依存しない総合的アプリオリにも見えるけど、そもそもその公理系自体が認識論的実践のなかで経験的に選択されてきたもので、”アプリオリ/アポステリオリの区分自体怪しくない?”みたいなクワイン的懐疑が結局起こります。
“公理”と”定理”の区分は総合的直観の関与の程度をグラデーションとして考えようとした感じで、後者がより総合的だけど、どちらも総合的ですが、現代数学からするとどっちも定理で区分に形式的な意味がありません。
物理学についてはニュートン力学がベースの理解だけど、もちろん観察についてはアポステリオリな要素もあるけど、法則の前提たる、それを構成する前提となる形式がアプリオリです。 物理法則はアポステリオリな観察と形式を前提とする理論化から構成されるけど、理論形成の形式的条件(空間・時間・因果性)はアプリオリです。
ウィトゲンシュタインの意味論、真理論の変遷
『論考』では論理や数学の必然性を「世界を写し取る像を可能にする言語の論理的形式」に基礎づけ、経験に依存しないアプリオリ性を認めていました。
後期のウィトゲンシュタインは、こうした経験に依存しない強いアプリオリな真理を前提せず、真理や必然性を 経験的・歴史的な実践の中での規則の運用 によって理解するようになる。必然性は、存在論的に厚いものではなく、規則に従う仕方が共同体的に安定しているがゆえに「必然」として経験されるものであり、その点でパトナムのいう「規約的真理」と通じるところがあります。
この「規則に依存する」という点には二層ある。日常言語の意味論は、自然言語共同体の生活形式や規範的実践に強く根ざしています。
論理学や数学は、形式体系の規則に従う実践に支えられている。ただしこの実践も、形式体系の理解・教育・承認を通して自然言語共同体に深く依存している。
したがって、日常言語と数学・論理の違いは「依存先がまったく異なる」ことではなく、実践が自然言語的生活形式にどの程度媒介されているかの度合いの違いにあります。
どちらの場合も、真理の必然性は「実践共同体における規則への従い方」の中に位置づけられるのです。
クワインのカント批判、ホーリズム
クワインは有名な論文「経験主義の二つのドグマ」(1951)で、カント的な「アプリオリの真理」を含む区分そのものを批判しました。
カント以来の区分は、分析/総合(分析的真理=概念の含意に基づく vs. 総合的真理=経験的な事実に依拠)、アプリオリ/アポステリオリ(経験独立的 vs. 経験依存的)というものでしたが、クワインはこの二分法は維持できないとします。
カントにとって「アプリオリな真理」は、少なくとも「分析的アプリオリ」と「総合的アプリオリ」に分けられました。クワインはまず「分析的真理」そのものを疑います。「すべての未婚の男は結婚していない」という命題は分析的に見えるものの、それも結局は「言語規約」「定義」に依存します。しかし定義も固定的なものではなく、理論全体の一部として修正可能です。 「分析的=定義によって必然的に真」という考え方は循環的だ、と批判します。
カントにとって核心なのは「総合的アプリオリ真理」(幾何学や因果律など)でした。しかしクワインにとって、数学や論理も「人間が採用する言語体系・理論全体の一部」であって、経験から完全に独立しているわけではありません。
その「ウェブ・オブ・ビリーフ(信念の網)」モデルでは科学的・論理的・数学的命題は、網の中心にある「改訂されにくい信念」ではあるものの、理論全体の調整次第では、論理や数学ですら修正され得る(極端なケースではユークリッド幾何学を非ユークリッド幾何学に置き換えるように)。よって、「絶対に経験から独立して妥当する真理=アプリオリ」は存在しません。
クワインは「どの命題も、経験に照らして個別にではなく、理論全体としてテストされる」と考えます。この立場は「ホーリズム」と呼ばれ、カントのような「認識能力に根ざしたアプリオリな形式」という考えを否定し、 代わりに「言語・理論全体が経験に照らして調整される」というダイナミックなモデルを提示したのでした。
クワインの批判の検討
クワインの”総合/分析”批判は自然言語や経験科学の理論語彙やカルナップ的規約主義に対しては妥当だけど、形式科学の内部ではちょっと過剰にも響くきます。形式科学のアプリオリ性への懐疑は刺さるけど、それも近似的には道具的な区分として評価はしうるものです。クワインの批判は”総合/分析””アプリオリ/アポステリオリ”の根拠への懐疑としては有効だけど、道具的に操作的な特徴付けとして承認することは可能ということです。
自然言語だと同一性は言語ゲーム論的な制度的・語用論的行為体系が中心的根拠で、科学的語彙と違って因果的連鎖で一貫した本質・自然種的強い同一性の核は考えにくく、意味論的統語論的同一性は因果的連鎖で再帰的に再生産される感じだから、実際カントの自然言語における分析的判断はあまり真理の強度を担保しません。
自然種とか、クリプキが言ってたときは最初の頃の”ミーム”くらい怪しい概念だったものの、ボイドとか実在論の人たちが精緻にしてて、経験科学の意味論においても安定的な因果的性質群のクラスターを考えうるから例えばそのような形で科学的実践のなかで”分析/総合”も評価しうるとは思うものの、それでも日常言語については難しいです。日常言語の語の使用は文脈依存・比喩的転用・社会的慣行変動に晒され、内包が実践の時間軸のなかで流動的再帰的に因果的に生成されるものです。
また自然種も性質のクラスター自体は実在論的なので観察からそれを確かめられず、語のはらむ要素の量化のドメインを特定困難で、あくまでも実践的安定性だから、形式科学とは同一性の安定性にちょっとグラデーションがあります。たとえば精神疾患の病名とか、日常言語よりは意味や指示の同一性が安定的だけど、形式科学ほどではありません。
クリプキの意味論、真理論
ウィトゲンシュタインが後期において捉えた「規約に依存する真理」は、共同体的実践における規則の安定的運用に基づくものであり、存在論的に薄い。これに対してクリプキは、「必然性」概念を可能世界意味論の枠組みで精緻化し、必然性を「剛性指示」と結びつけて理論化した。
クリプキにとって「A=Bであるならば、AがBであることは必然的である」。たとえば「水=H₂O」は経験的に発見されたが、いったん「水」という語がH₂Oを指すと決まれば、それはどの可能世界でも成立する「必然的だがアポステリオリな真理」となる。
つまり、クリプキは 言語共同体における命名の仕方(名付け時点の固定)が、その後どの可能世界を考えても移行可能なかたちで対象を指し続けるとみなし、ここに「指示の剛性」を見出した。
クリプキは、固有名=固定指示子 (rigid designator) が自然種の持つ本質と直結していると考える。たとえば「水」という語がH₂Oを指すと決まった以上、どの可能世界においても「水=H₂O」であり、この同一性は自然種の本質に基づく必然性を表す。
パトナムの意味論、真理論の変遷
パトナムは、活動時期によってスタンスが違って、有名な双子地球実験は、初期の意味論における強い本質主義、外在主義的スタンスを体現するものです。
それで初期から意味論について、規約と自然種的本質の二元論的理解をしていたのはそうなんですが、次第に規約の方に重きを置くようになります。
中期では、確かに初期には「水=H₂O」という形で答えたものの、実際には我々の科学的理論が H₂O を水と見なしているにすぎない。もし科学理論が違っていたら、同じ外見の液体を別の仕方で分類していた可能性もある。だから、双子地球で人々が「water」と呼んでいる液体を XYZ と科学的に特徴づけたとしても、それは彼らの理論枠組みに依存するのであって、「絶対的に誤り」というよりは「枠組みの違い」と、見ると思います。
後期には、地球人が「水」と呼ぶものは H₂O、双子地球人が「water」と呼ぶものは XYZ。だが、その違いは形而上学的な「本質」の問題ではなく、言語共同体がどのように実践的に参照を固定してきたかの問題にすぎない。双子地球人の言語実践は XYZ を中心に組織されているので、それを「water」と呼ぶのは正当である。地球人にとっては H₂O が「水」。どちらもその共同体の実践において正しい、と見ると思います。
真理一般についても、規約と自然種的本質の折衷的な二元論的スタンスが、規約優位に移っていく感じです。
中後期パトナムのスタンス
パトナムは、ウィトゲンシュタイン的な「言語ゲーム」の発想を吸収しつつも、それを言語ゲーム的な極端な規約主義にはせず、「内在的に客観的な真理」=「枠組みに内在し、経験や実践に制約される真理」を認め続けた、って感じです。結局、実践的な部分を重視して、強い科学的・形而上学的実在論を規約主義と折衷して、留保するようになる感じと思います。
精神医学の例がわかりやすいかもです。「ASD(自閉スペクトラム症)」やその他の診断名・カテゴリーは、精神医療共同体の合意や診断基準(DSMやICD)に基づいて定められます。そのため、診断名や基準は時代や文化によって変化します(例:自閉症スペクトラムの定義が拡張されたり、ADHDの基準が改訂されたり)。
しかし、患者が経験する行動・認知・感情のパターンは、単なる規約に恣意的に依存しているわけではありません。それらは人間の脳や心理のあり方に制約されて現れます。ただし、そのパターンが「症状」として切り出され、診断カテゴリーに組み込まれる仕方は、文化的・社会的文脈に大きく左右されます。
パトナムの中期以降の立場で言えば、診断名やカテゴリーは「言語ゲーム的に規約に依存して柔軟に変わる」ものです。しかしそれは、世界に向き合う私たちの実践の中で、観察可能な現象(行動パターンや認知の傾向)に拘束されながら成立しています。言い換えれば、診断基準やカテゴリーは歴史的・社会的に相対化されうるが、その内側では、経験に基づく客観性や真理性が成立しているのです。
中〜後期のパトナムにとり、枠組みや言語ゲームに依存しない、純粋にアプリオリな真理は存在しない、とウィトゲンシュタイン同様に否定します。ただし全部が恣意的な相対主義でもなく、私たちの実践や経験に基づいた枠組み内での客観性・真理性 は確立できる、という立場です。
たとえば 論理法則(排中律など)は「世界に刻まれた絶対的必然性」ではなく、私たちの推論実践を支えている 規則の体系 に基づいて「必然的」とされます。精神医学の例なら、「ASDの診断基準に当てはまるなら、ASDと診断される」という必然性も、DSMやICDといった 規約に依存して成り立つ必然性です。
ただし、規約そのものは経験的実践に拘束されていて、全く根拠なく自由に変えられるものではありません。
パトナムの中期の真理論(内在的実在論)は、科学的対象の存在を否定するものではなく、形而上学的な「対応としての客観的真理」を退ける立場。
真理は、観測や認識の実践を通じて構成的に正当化されるものであり、その必然性も、歴史的に共有された規約の中で合理性や自然との関わりによって訂正可能なものとして理解される。これは、規約主義的要素とプラグマティック自然主義の折衷といえます。
形式的な哲学史区分では、パトナムの中後期は 「科学的反実在論」 に括られるのが普通。ただし自身は「実在論の一種」と見なしており「規約主義や相対主義の極端な形」と区別することは重要です。基本的にクワイン以降の流れで、観察、観測や認識論的正当化のプロセスのはらむ不確実性を内在的に説明し、不可知論的で検証困難な科学的実在論の想定する強い対応説へのコミットメントを避けようとするスタンス。
一般的に科学的実在論は、存在論、意味論、認識論における科学的対象との対応説を唱える立場と形式的に分類されるから強い主張です。
パトナムも対応説を避けて認識論的不確実性を内在的に説明します。戸田山先生のは対応説自体をデフレ解釈して、科学的実在論をとるスタンスだけど、形式的には反実在論な感じです。
科学的実在論のいう「客観的真理はある」は、存在論、認識論、意味論において強い主張なので、それをパトナムは否定するから形式的には反実在論だけど、認識論の不確実性を内在化したかたちで、制度や枠組み(科学共同体、言語実践、探究の規範)を通じて、客観的真理を承認します。
意味論では「対応説的意味論」を退けて、内在的な枠組み依存性を強調し、認識論では「不確実性を内在化した制度的客観性」を強調し、存在論では「理論に基づいた実在」を受け入れるが、それを神の視点から保証しない、くらいの感じで、存在論はそんなに科学的実在論と大きな距離はありません。
参考文献
・飯田隆 (著)『言語哲学大全II 意味と様相(上)』『 言語哲学大全Ⅲ: 意味と様相(下)』
















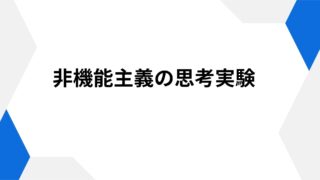





コメント