コンテンツ
前史としてのヘーゲル
実存主義の前史としてヘーゲルがいます。ヘーゲルはカントを批判的に継承しました。
カントにとって「物自体」は、「われわれの感性的認識の外にあるが、思考の対象としては考えられる」ものです。経験的に知ることはできない(現象ではない)ものの、理性上は想定されざるをえない(認識の限界を定める)ものです。要するに、物自体は本質的なものでありながら、到達不能なものです。現象はそれを表してはいるものの、完全には与えません。「本質=不可視の根拠」「現象=その現れ」といった二項構造が立っています。
ヘーゲルは、カントの「物自体」「到達不能な本質」を否定します。ヘーゲルにとって「本質」は、「現象」から分離した彼岸ではなく、 現象の内において自己を媒介的に顕現する運動そのものです。本質は隠れているのではなく、現象のなかで自己を展開し、その「現れ」を通じてしか存在せず、現象こそが本質です。ここで「本質=物自体」という対立構造は解体されます。本質は現象の背後ではなく、現象の内的構造になります。
ヘーゲルの『大論理学』では、「本質」は「存在」を止揚した次の段階として現れます。つまり、本質とは単なる実体や固定的性質ではなく、自己を媒介し、自己を通して現象として現れる契機です。本質は、存在の背後にある隠れた真理ではなく、むしろ現象を通じて自己を表現・自己展開する「弁証法的過程」そのものです。 「存在=即自的」、「本質=対自的」、「概念=即自かつ対自的」といった自己運動の段階づけの中に置かれています。
ヘーゲルにとっての「本質」とは、単なる属性ではなく、存在の内的必然性であり、現象との媒介的関係によって自己を顕現する統合的構造です。
キルケゴールの実存主義
キルケゴールは、ヘーゲル的体系哲学に対する批判者であり、「普遍的人間」ではなく、「神の前に立つ単独者」を哲学の中心に据えました。キルケゴールは真理とは客観的に把握される体系的知ではなく、個人がどのように生き、選び、神と関わるかという存在の仕方そのものとします。
キルケゴールが用いる「実存」は、「抽象的な人間性」ではなく、時間の中で選択し、苦悩し、神の前に立つ“私”を指します。人間は思弁的理念によってではなく、有限性と無限性、時間性と永遠性、自由と必然の矛盾の中で生きており、その「緊張」こそが実存の本質です。
キルケゴールは人間の生の在り方を三段階に整理します。審美的段階 (快楽・感覚・享楽に生きる。自己を見出せず、無意味に陥る) 、倫理的段階(道徳的責任・義務を引き受ける。だが普遍的倫理に閉じ込められる)、宗教的段階(神の前に単独者として生きる。理性や倫理を超えた信仰の飛躍を行う)です。
最後の段階で、アブラハムがイサクを捧げる行為が象徴的に扱われ、倫理的普遍性(他者を殺してはならない)を一度中断し、絶対的神との関係においてのみ成り立つ単独者としての選択が肯定されます。
キルケゴールの哲学は、根本的にヘーゲル的弁証法への拒否から出発しています。ヘーゲルは「矛盾」を統合し普遍的体系に還元しようとしました。キルケゴールは「矛盾」を人間の生の内在的構造として受け止めたのです。したがってキルケゴールにとって、人間の真理は普遍の中にではなく、非普遍的で孤独な選択の中にあります。「主体性の真理」「存在の真理」というモチーフが生まれます。
ハイデガーの実存
ハイデガーとサルトルはいずれもヘーゲルの哲学から強い影響を受けています。両者に共通するのは、ヘーゲル的な「意識の自己関係性」と「否定性」、「歴史的展開」という発想を出発点にしている点です。存在や意識は単なる静的な実体ではなく、自らを超えて他者や世界との関係のなかで構成される運動的なものとして理解されます。
しかし、ハイデガーにとってこのヘーゲル的運動は存在の意味を覆い隠す形而上学的誤りの極致で、サルトルにとってはむしろ自由と他者関係の弁証法として再生されるべき契機です。
ハイデガーは、ヘーゲルが存在を思惟あるいは概念の自己運動に還元したとみなし、それを「存在忘却」の最終段階として批判しました。ハイデガーにとって重要なのは、存在を思考の対象や意識の自己展開としてではなく、それらが成り立つ以前の「開け」として捉えることです。
『存在と時間』における現存在は、この「存在の開示」に関わる存在者として規定され、ヘーゲル的な自己意識の弁証法を「概念的運動」から「存在の自己開示」へと転換します。ハイデガーは、ヘーゲルの否定性や歴史性を受け継ぎつつも、それを思惟の枠組みから解放し、存在論的次元へと引き戻したのでした。
サルトルの実存
サルトルは、ヘーゲルをとくに『精神現象学』の主人と奴隷の弁証法を通じて受け入れます。サルトルにとって意識は常に他者との関係において自己を確立しようとする自由な運動で、他者の「眼差し」は自己を対象化し、葛藤と承認の契機をもたらします。サルトルにおいて「否定性」は、自己が自己を超えて投企する自由の根拠となり、「歴史性」は人間が状況を超えて自己を形成する契機として理解されます。
ハイデガーはヘーゲルを存在を思惟に還元した最後の形而上学者として批判的に継承し、存在の開示という非概念的次元へ転回させたのに対し、サルトルはヘーゲルの弁証法を自由と他者関係の倫理的構造として再解釈し、人間中心的な実存主義へと展開したのでした。
カミュの実存と不条理
カミュの思想は、20世紀の実存主義的文脈に位置づけられながらも、サルトルとは異なり「自由の哲学」よりも「不条理」の哲学です。
カミュの出発点は、人間が世界に意味を求める存在であるにもかかわらず、世界が沈黙し何の応答も与えないという根本的な断絶である「不条理」の自覚にあります。人間の理性が秩序や意味を渇望するほどに、無意味で沈黙した世界との対峙は鋭くなり、その緊張が人間の生の根底を規定します。
カミュは、この不条理の発見を悲観でも虚無でもなく、思考の出発点とします。カミュにとって問題は「生きる意味がないなら、なぜ自殺しないのか」という問いです。『シーシュポスの神話』で示された答えは、「不条理を認めながらも、それに屈しないで生きること」でした。
シーシュポスは永遠に岩を押し上げるという無意味な運命を与えられているものの、彼がその運命を自覚し、それを引き受けてなお笑うとき、彼の生はもはや敗北ではなく、抵抗としての肯定に転じます。カミュにとって不条理を生きるとは、意味を持たない世界のなかで意味を創ろうとせず、ただその無意味さのなかに生の強度を見出すことです。
この不条理の意識はやがて「反抗(」の思想へと展開します。『反抗的人間』においてカミュは、絶対的な意味や価値を否定する立場をさらに進め、そこから無制限な破壊やニヒリズムに陥ることを拒みます。カミュにとって反抗とは、世界の不正や不条理に対してこれ以上は許さないと言うこと、すなわち人間的尊厳の最低限の境界を宣言する行為です。
反抗は、絶対的価値の欠如のなかで、相対的価値を創造する人間の倫理的行為で、それは意味のない世界に対する、人間の意味への固執です。したがってカミュは、虚無主義を拒否しつつも宗教的救済や形而上学的秩序にも依らない、限界のなかの倫理を提示します。
『ペスト』や『正義の人々』などの作品においてカミュは、この反抗を共同性の次元へと拡張します。そこでは個人の抵抗が他者への連帯へと変わり、他者の苦痛を自らの苦痛として引き受ける行為に倫理の根拠を見出すのです。カミュの「反抗」は、孤立した個の自由ではなく、人間的連帯の倫理的基盤です。
カミュの思想は、「神なき世界」において人間がなお誠実に生きうる可能性を模索するものです。サルトルのように自由の形而上学を構築することも、ハイデガーのように存在論的基礎を探ることもせず、むしろ世界の沈黙と有限性を正面から引き受け、それでもなお「生きるに値する」と言い切る勇気を哲学の中心に据えました。
実存をめぐるスタンスの相違
キルケゴール、ハイデガー、サルトルはいずれも、伝統的形而上学が人間を普遍的本質や理性の一形式として捉えてきたことに対して、個々の存在の現実的あり方である「実存」を中心に据えようとしたという点で共通しています。しかしその「実存」と「本質」の関係づけ方は、宗教的救済・存在論的開示・倫理的自由という異なる関心に導かれているのです。
キルケゴールにおいて「実存」は、抽象的理性や普遍的倫理のうちに吸収されえない個人としての生の内面的あり方を意味します。キルケゴールにとって「本質」とは理念や普遍性を指すものの、実存的人間は常にそのような本質から逸脱し、矛盾と不安のなかで自己を形成します。したがって人間は本質に即して生きる存在ではなく、神の前に単独者として生きる存在であり、その実存の根底には「絶望」と「信仰」の飛躍があります。キルケゴールにおいて実存は、本質を超え出る宗教的出来事として理解されるのです。
ハイデガーは、キルケゴールの「実存」概念を哲学的に脱宗教化し、存在論的次元へと転化します。『存在と時間』において現存在は、「自分がいかに存在するか」を問う唯一の存在者であり、その意味で「実存的」です。
しかしハイデガーにとって「本質」とは固定的な性質の集合ではなく、むしろ可能性としての存在様態です。ハイデガーは人間の本質を超越的理念ではなく、自己を投企し時間的に開示していく存在のあり方に見いだします。ここでは実存と本質の区別そのものが解体され、両者は「存在の開示」という動的過程のなかで重なり合うのです。
サルトルは、ハイデガーの実存概念を人間中心的かつ倫理的に再構成します。彼の有名な命題「実存は本質に先立つ」は、神のいない世界において、人間にはあらかじめ定められた本質が存在せず、自己のあり方を自らの行為によって創り出すしかないという意味です。
人間は「投げ出された存在」であると同時に、絶対的な自由によって自己を規定する責任を負います。したがってサルトルにおいて本質とは、実存的選択の結果としてあとから形成されるものであり、実存は常にそれに先行します。ここで「実存」は宗教的飛躍や存在の開示ではなく、倫理的自由と自己形成の契機として理解されます。
まとめるとキルケゴールでは実存が神の前での内面的飛躍として、本質を超える宗教的契機として現れ、ハイデガーでは存在の意味の開示として本質と実存の形而上学的区別が解体され、サルトルでは自由な主体の自己創出として実存が本質に先立つ倫理的原理となります。
実存と不安
不安は結構、実存主義の思想家、哲学者でニュアンスがそれぞれ違います。
ハイデガーだと不安は無への開示で、世界との意味的繋がりが崩れることで主体が実存への問いを持つ契機です。サルトルは世界とのコミットメントで実存的主体が本質を欠く自由と責任に対して抱くもの、カミュだと不安についてそもそもあまり語らないけども人生や生の外在的な無意味さ(不条理)へ不安が起こるであろう感じです。

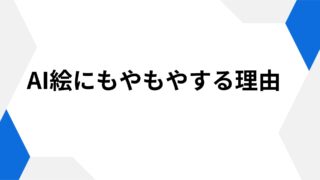











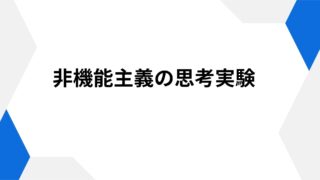








コメント